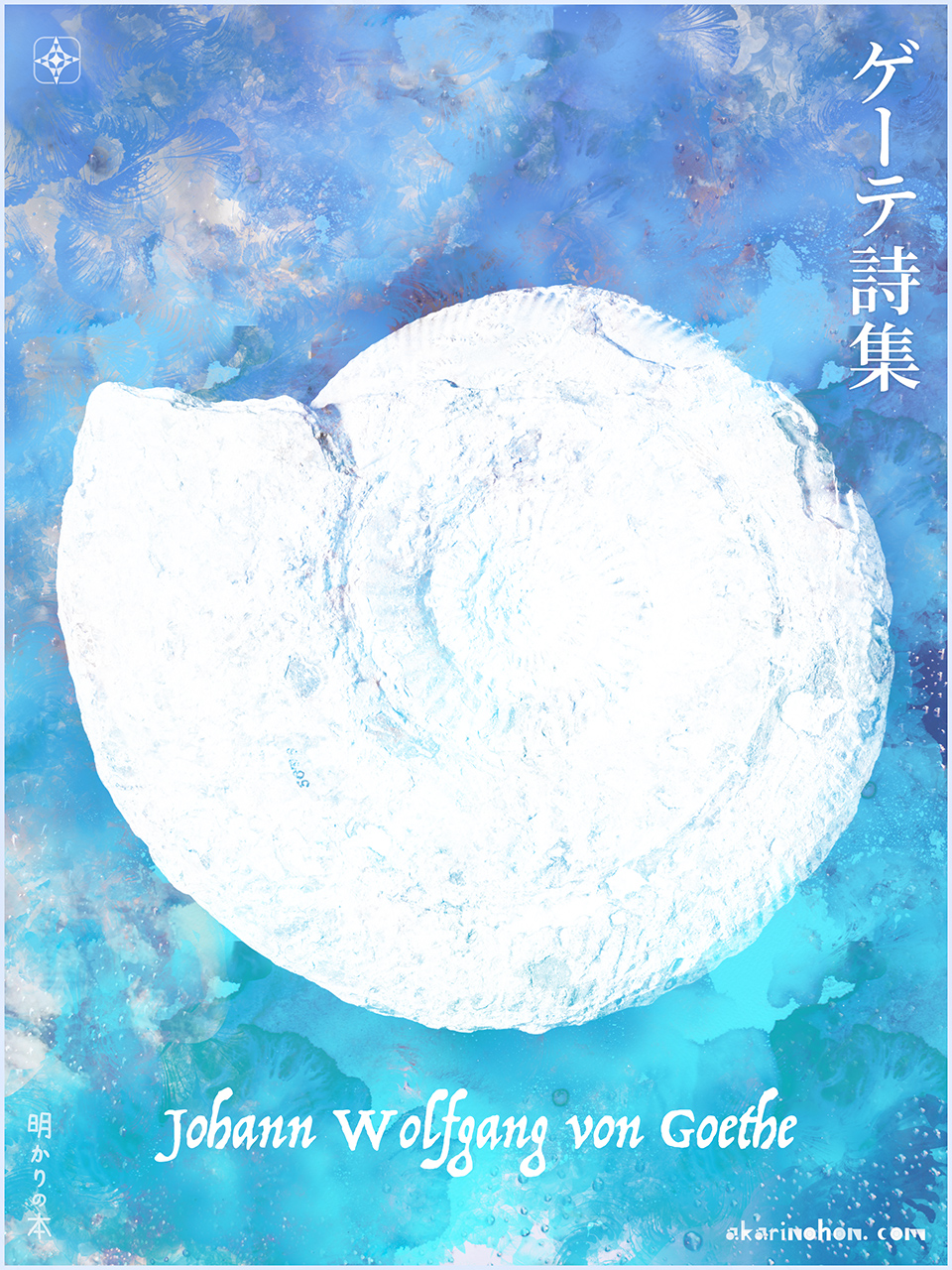お気に入りに追加
お気に入りに追加
今日は泉鏡花の「月令十二態」を公開します。縦書き表示で全文読めますよ。
これは泉鏡花が、四季を記している短編です。月令とは、どういう意味かというとwikipediaにはこう記されています。
月令(げつれい、がつりょう)とは漢籍の分類のひとつで、月ごとの自然現象、行事、儀式、農作業などを記したものを言う。時令(じれい)とも呼ぶ。古代の制度・習俗や農業技術を知るために重要である。
ところで、新元号について、やっぱり新聞記者が学者に取材した記事が興味深くて、万葉集の
「于時、初春令月、氣淑風和、梅披鏡前之粉、蘭薫珮後之香。」
時に、初春の令月にして、気淑く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫す。 から引用したのだとか、さかのぼると中国の張衡が書いた「帰田賦」にこの令和の語源があるのだそうです。この箇所です。
「於是仲春令月 時和気清 原隰鬱茂 百草滋栄」
仲春の令月に時は和し気は清む、という意味で使われたそうです。「帰田」は「郷里の田園に帰って農事に従うこと」を意味するわけで、そこで春三月のよい季節(令月)に和らぐ……令和の語源はこの辺りにあるのかもしれません。これを元号に推薦した学者はすごく文学的な人だなあと思いました。令月ってはじめて知りましたけど、すてきな言葉ですねえ。(※誤記を訂正しました)
他にもwikipediaには、まったく知らなかったことが記されていました。自分の名前が入ってると嬉しい、という話しは、平成元年にも聞いたことがあるなあ、なつかしい、と思いました。ところで、戦後5年の1950年ごろには日本も世界に倣って元号を廃止すべきと考えた学者さんがいっぱい居たようです(今もおそらく)。世界中に元号はあったわけですけど、20世紀末や21世紀に元号を使っている地域はもうどこにもなくって、日本だけがこれをやっているんだそうです。
えーと、それで泉鏡花は、月令について、12カ月ぶんの美しい自然と暮らしを描写しています。10月が印象に残りました。
雲往き雲來り、やがて水の如く晴れぬ。白雲の行衞に紛ふ、蘆間に船あり。粟、蕎麥の色紙畠、小田、棚田、案山子も遠く夕越えて、宵暗きに舷白し。
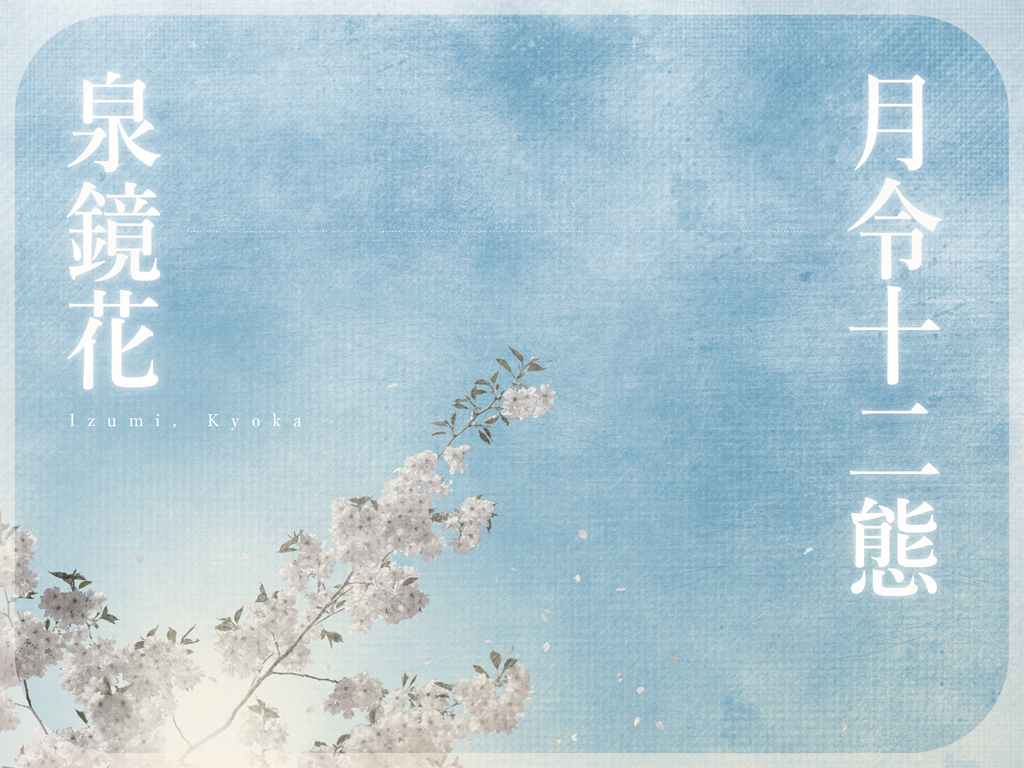
以下の「シンプル表示の縦書きテキスト」をご利用ください。(縦書きブラウザの使い方はこちら)
https://akarinohon.com/migration/getsure_jyunitai.html
(約10頁 / ロード時間約30秒)
★シンプル表示の縦書きテキストはこちら
明かりの本は新サイトに移行しました!
URLの登録変更をよろしくお願いいたします。
明かりの本 新サイトURL
https://akarinohon.com
(Windowsでも、なめらかな縦書き表示になるように改善しました!)
appleのmacやタブレットやスマートフォンなど、これまで縦書き表示がむずかしかった端末でも、ほぼ99%縦書き表示に対応し、よみやすいページ構成を実現しました。ぜひ新しいサイトで読書をお楽しみください。
ここからは新サイトの「ゲーテ詩集」を紹介します。縦書き表示で読めますよ。
幼かった頃の夢想のことを、ゲーテは「黄金の空想よ」と記します。ゲーテの詩には、神話的なものと理知的なものが混在していて、これが魅力のように思います。ゲーテはゲルマン神話と、とくにギリシャ神話の影響が色濃いようです。
この詩集は生田春月が翻訳をした作品です。ゲーテは政治家としても活躍し、かのナポレオンからも尊敬されていた作家で、その言葉を詩で楽しめるというのは、なんだか嬉しいように思います。
装画をクリックするか、ここから全文を読んでください。 (使い方はこちら) (無料オーディオブックの解説)
(総ページ数/約10頁 ロード時間/約10秒)
『ゲーテ詩集』全文を読むにはこちらをクリックしてください
・top page ・本屋map ・図書館link ★おすすめ本 ★書籍&グッズ購入
Similar Posts:
- None Found