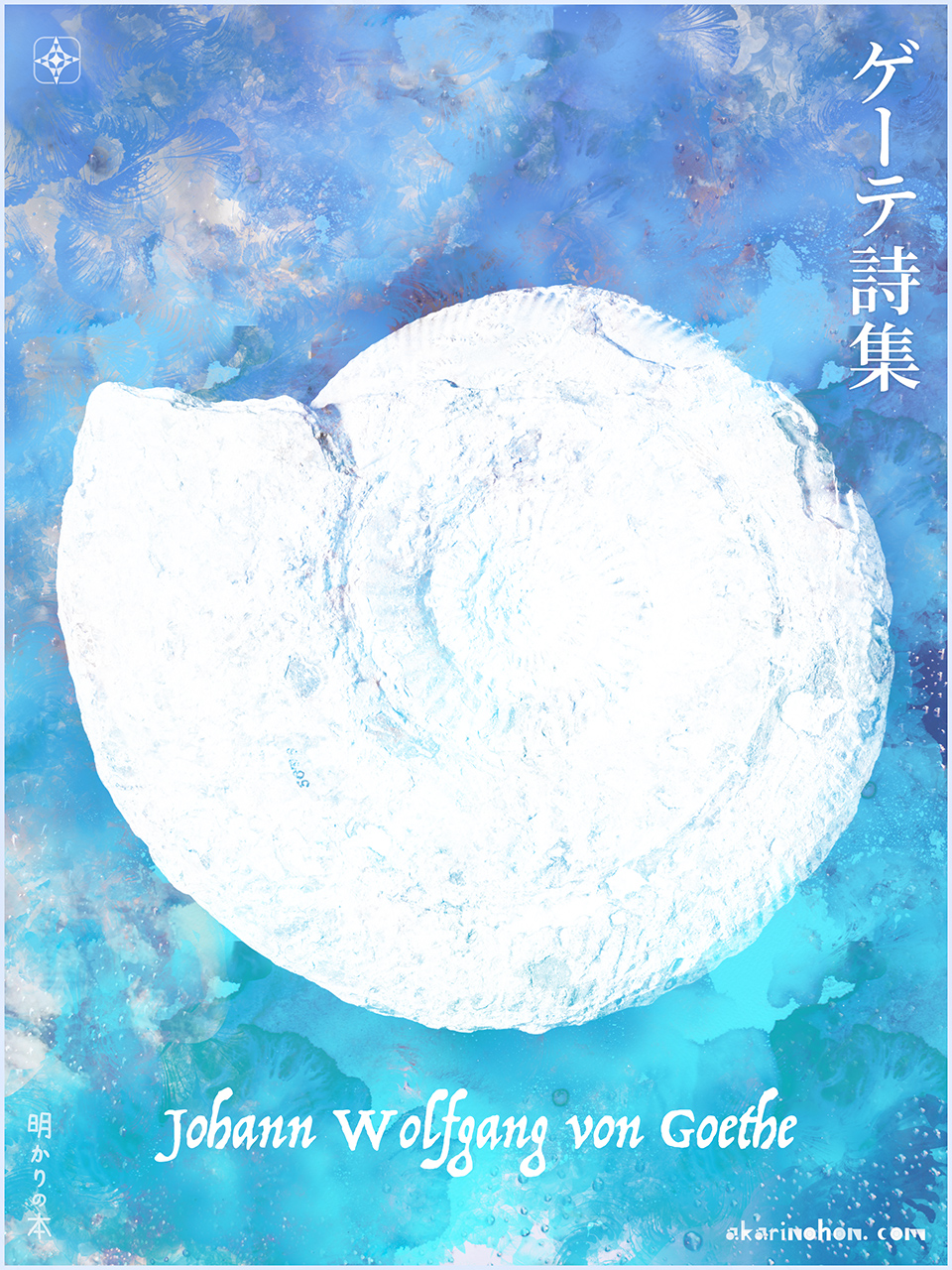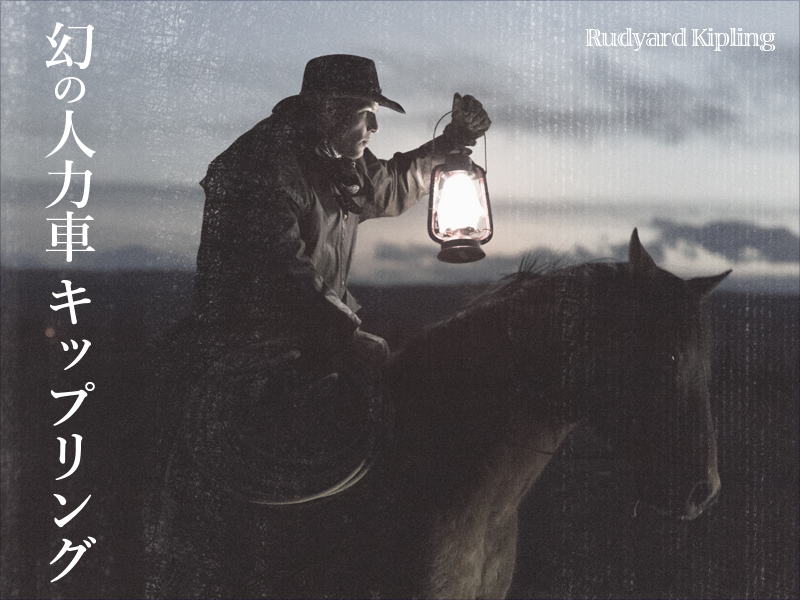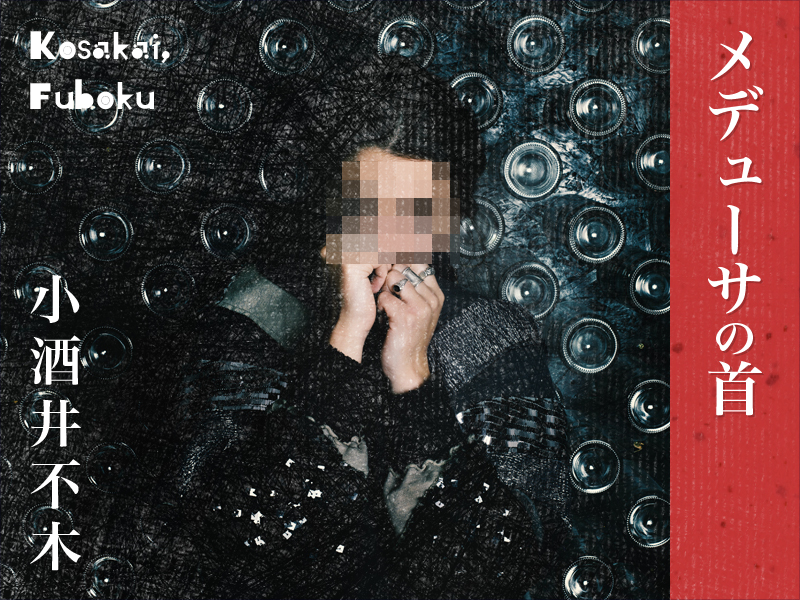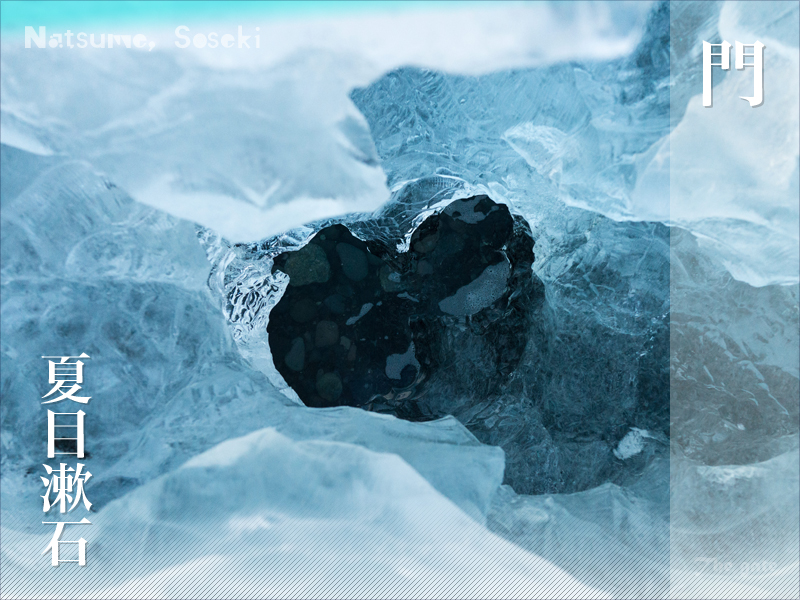今日は夏目漱石の『門』その13を公開します。縦書き表示で全文読めますよ。
妻の御米は健康を取りもどし、世間では正月を迎えようとしています。まったくどうでもいい話しなんですが、自分の人生でこういう通過点があったら、良いのになあーとか思いながら読んでいました。
物語の本筋とは関係のない描写なんですが、宗助は床屋へ行って、己の姿を鏡で見た。その時に用いる「影」という言葉が、印象に残りました。絵にしたら、なぜか鏡に写る自分の顔だけは、まっ黒であるという描写になるだろうなあ、と思いました。こういう本文なんです。
ようやく自分の番が来て、彼は冷たい鏡のうちに、自分の影を見出した時、ふとこの影は本来何者だろうと眺めた。首から下は真白な布に包まれて、自分の着ている着物の色も縞も全く見えなかった。その時彼はまた床屋の亭主が飼っている小鳥の籠が、鏡の奥に映っている事に気がついた。鳥が止り木の上をちらりちらりと動いた。
ふつうなら、影とは書かないところで、漱石が影、と記しているのが印象に残るんです。「鏡にうつる姿」とか「鏡像」とか書くんだと思うんです。
情景としては太陽の光が床屋に差しこんで、逆光になっているところを文章にしているのかもしれないです。漱石はおそらく、鏡に写る己の写像は、これは実態が無い、という意味で、影と記している。他人が見て、他人が認識した自己の姿も、言ってみれば他人の眼球の内部で描きだした写像にすぎないわけで、漱石はたった一文にもずいぶん豊かなイメージを流し込めるんだなあーと、読んでいて呻りました。漱石にはどうもこう、カフカとの共通項を感じる、と思うのは、ぼくだけなんでしょうか。
中盤の、山奥からきた織物屋の行商人が、暮のさしせまった頃に反物を売り歩いて、これを売り切ってゆく姿が描かれるんですが、じつに粋な描写でした。都市と田舎の暮らしぶりの落差も鋭く切りとられているんです。漱石の描きだす、対比の妙というのが冴える第13章でした。後半の夫婦の描写が、ほんとに良いんですよ。ほんとに。

以下の「シンプル表示の縦書きテキスト」をご利用ください。(縦書きブラウザの使い方はこちら)
https://akarinohon.com/migration/mon13.html
(約30頁 / ロード時間約30秒)
★シンプル表示の縦書きテキストはこちら (横書きはこちら)
明かりの本は新サイトに移行しました!
URLの登録変更をよろしくお願いいたします。
明かりの本 新サイトURL
https://akarinohon.com
(Windowsでも、なめらかな縦書き表示になるように改善しました!)
appleのmacやタブレットやスマートフォンなど、これまで縦書き表示がむずかしかった端末でも、ほぼ99%縦書き表示に対応し、よみやすいページ構成を実現しました。ぜひ新しいサイトで読書をお楽しみください。
ここからは新サイトの「ゲーテ詩集」を紹介します。縦書き表示で読めますよ。
幼かった頃の夢想のことを、ゲーテは「黄金の空想よ」と記します。ゲーテの詩には、神話的なものと理知的なものが混在していて、これが魅力のように思います。ゲーテはゲルマン神話と、とくにギリシャ神話の影響が色濃いようです。
この詩集は生田春月が翻訳をした作品です。ゲーテは政治家としても活躍し、かのナポレオンからも尊敬されていた作家で、その言葉を詩で楽しめるというのは、なんだか嬉しいように思います。
(総ページ数/約10頁 ロード時間/約10秒)
『ゲーテ詩集』全文を読むにはこちらをクリックしてください
・top page ・本屋map ・図書館link ★おすすめ本 ★書籍&グッズ購入