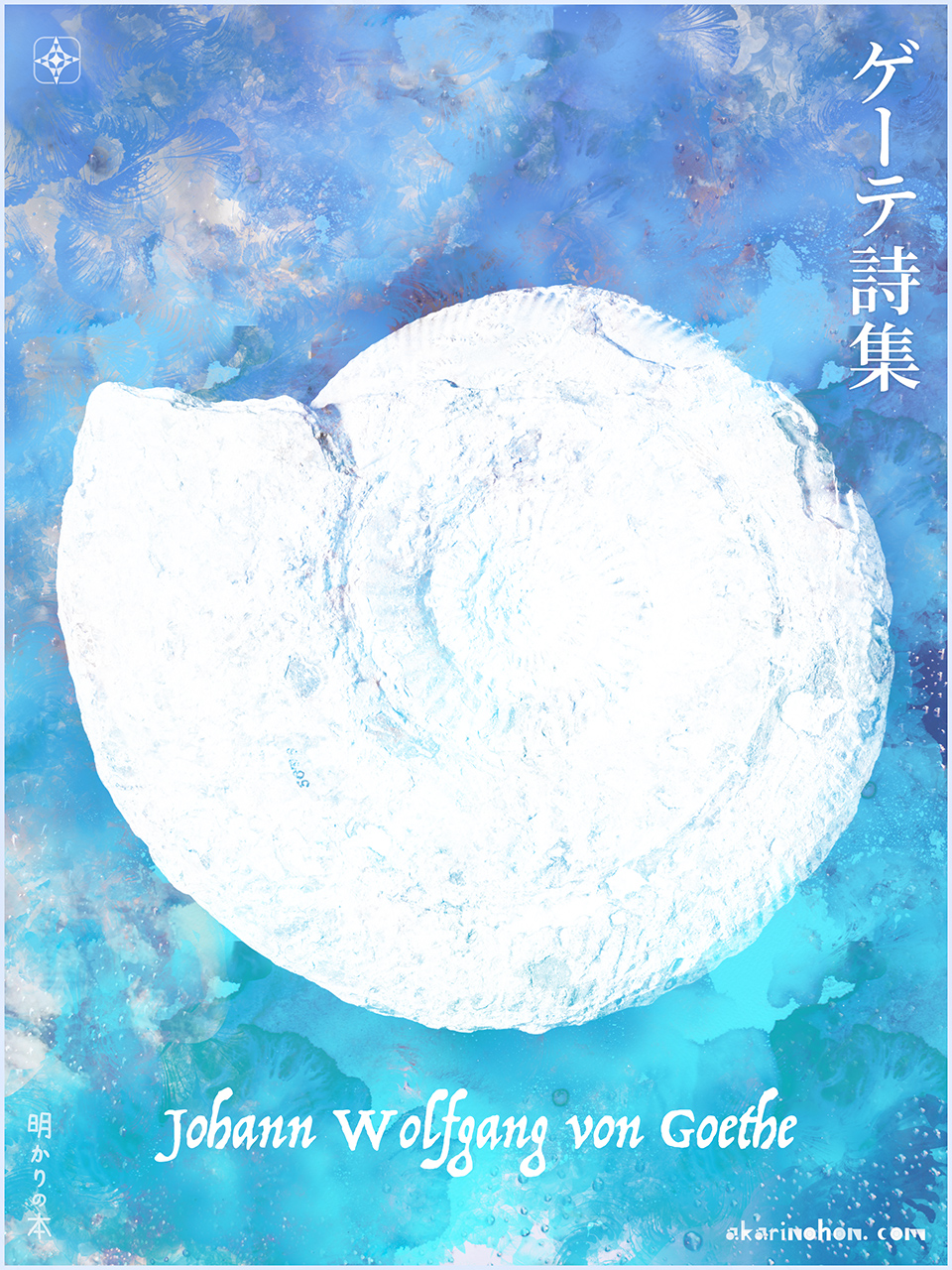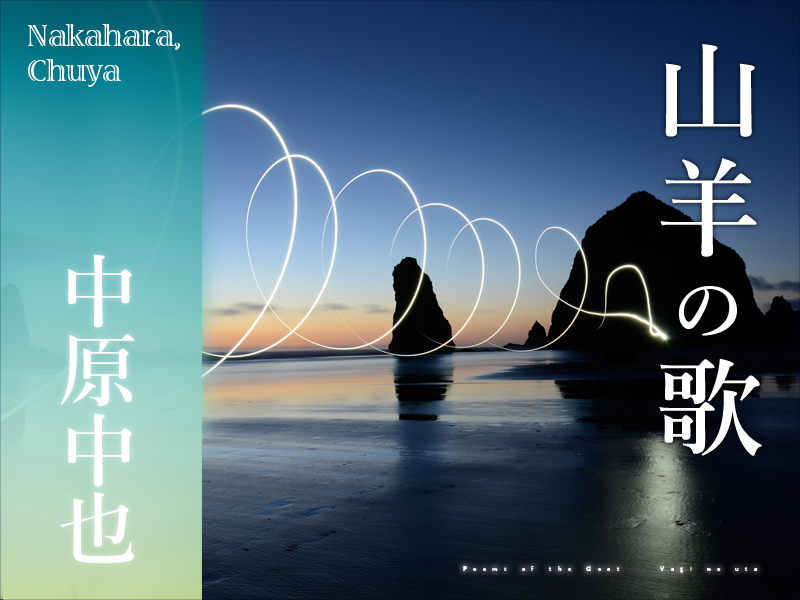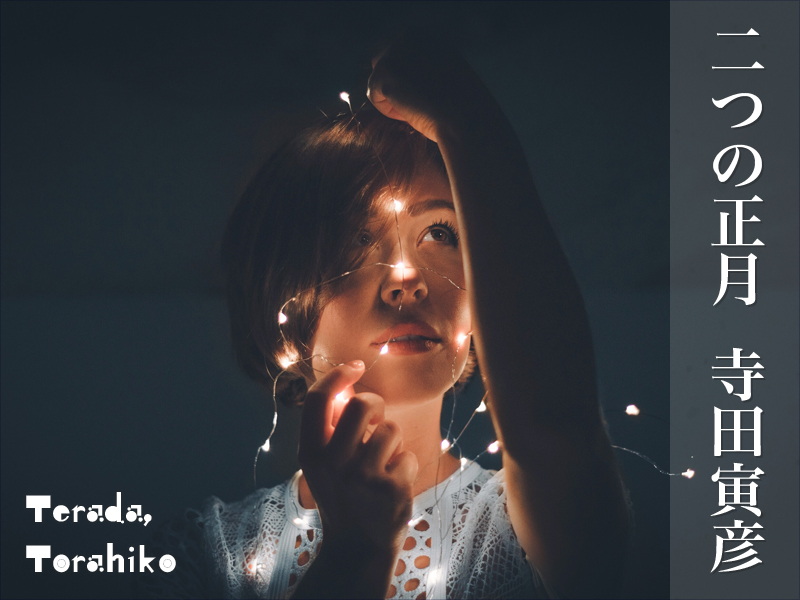今日は芥川龍之介の「永久に不愉快な二重生活」を公開します。縦書き表示で全文読めますよ。
二という数字で思いつくのは、「二心」とかちょっと危うい意味のものだったり、あるいは井伏鱒二とか、小林多喜二といった文豪の名前とかを思い浮かべるんですが、芥川龍之介は芸術と人生の二面性について、この短い手紙で論じています。
これは……どういう状況で書かれたものかちょっとよく判らないんですけど、ずいぶん率直に、手短に論じています。後学の知人からの質問に対する答えとして、芥川はこれを書いているようです。
芥川龍之介の経歴を改めて調べてみると、英語に携わりながら文学に入っていって、英語教師をしてから新聞社に入るという、漱石と同じ道のりを辿っていて、一つ異なっているのは、結婚相手も就職先も、海軍と関わりが深かった、という点なんです。森鴎外のように完全な軍人というわけではないんですが、芥川龍之介は軍(とくに海軍)と深い関わりにありながら、このことについてはあまり論じていないように思えるんです。ただ、漱石がいちばん好きだったからには、漱石と同じように、戦争を忌避しようという思いが強かったはずだと思うんです。この短い随筆でも、不愉快の理由が軍国にあるなどとは、芥川龍之介は一言も言っていません。
この随筆を読んでいて、井伏鱒二の言葉を思いだしました。こういうのです。
僕は、はっきり口に出して云った。
荷物を川のなかへ放りこんでやろうかと思った。戦争はいやだ。勝敗はどちらでもいい。早く済みさえすればいい。いわゆる正義の戦争よりも不正義の平和の方がいい。
(井伏鱒二著「黒い雨」より)
これは、キケロの言葉から着想を得た文章なんだそうです。ちょっともはや芥川の随筆と無関係なはなしになってしまいました……。
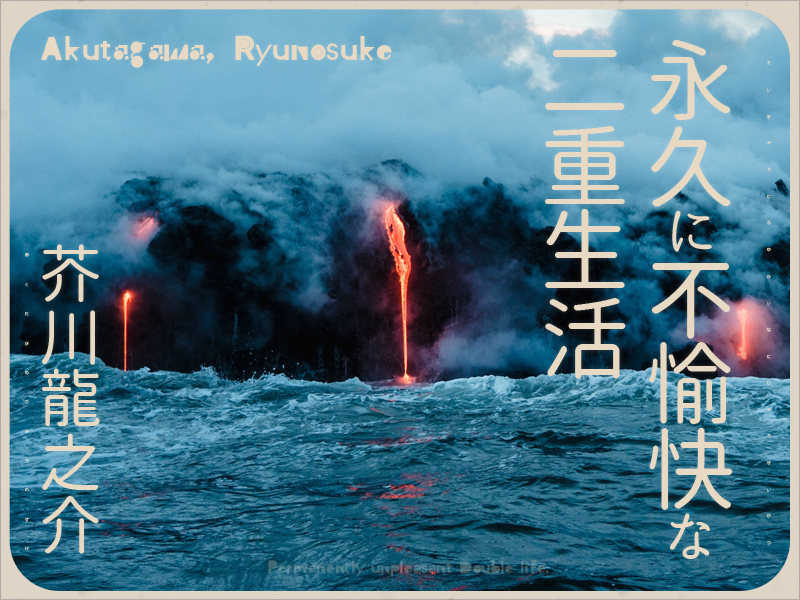
以下の「シンプル表示の縦書きテキスト」をご利用ください。(縦書きブラウザの使い方はこちら)
https://akarinohon.com/migration/eikyuni_fuyukaina.html
(約1頁 / ロード時間約30秒)
★シンプル表示の縦書きテキストはこちら
明かりの本は新サイトに移行しました!
URLの登録変更をよろしくお願いいたします。
明かりの本 新サイトURL
https://akarinohon.com
(Windowsでも、なめらかな縦書き表示になるように改善しました!)
appleのmacやタブレットやスマートフォンなど、これまで縦書き表示がむずかしかった端末でも、ほぼ99%縦書き表示に対応し、よみやすいページ構成を実現しました。ぜひ新しいサイトで読書をお楽しみください。
ここからは新サイトの「ゲーテ詩集」を紹介します。縦書き表示で読めますよ。
幼かった頃の夢想のことを、ゲーテは「黄金の空想よ」と記します。ゲーテの詩には、神話的なものと理知的なものが混在していて、これが魅力のように思います。ゲーテはゲルマン神話と、とくにギリシャ神話の影響が色濃いようです。
この詩集は生田春月が翻訳をした作品です。ゲーテは政治家としても活躍し、かのナポレオンからも尊敬されていた作家で、その言葉を詩で楽しめるというのは、なんだか嬉しいように思います。
(総ページ数/約10頁 ロード時間/約10秒)
『ゲーテ詩集』全文を読むにはこちらをクリックしてください
・top page ・本屋map ・図書館link ★おすすめ本 ★書籍&グッズ購入