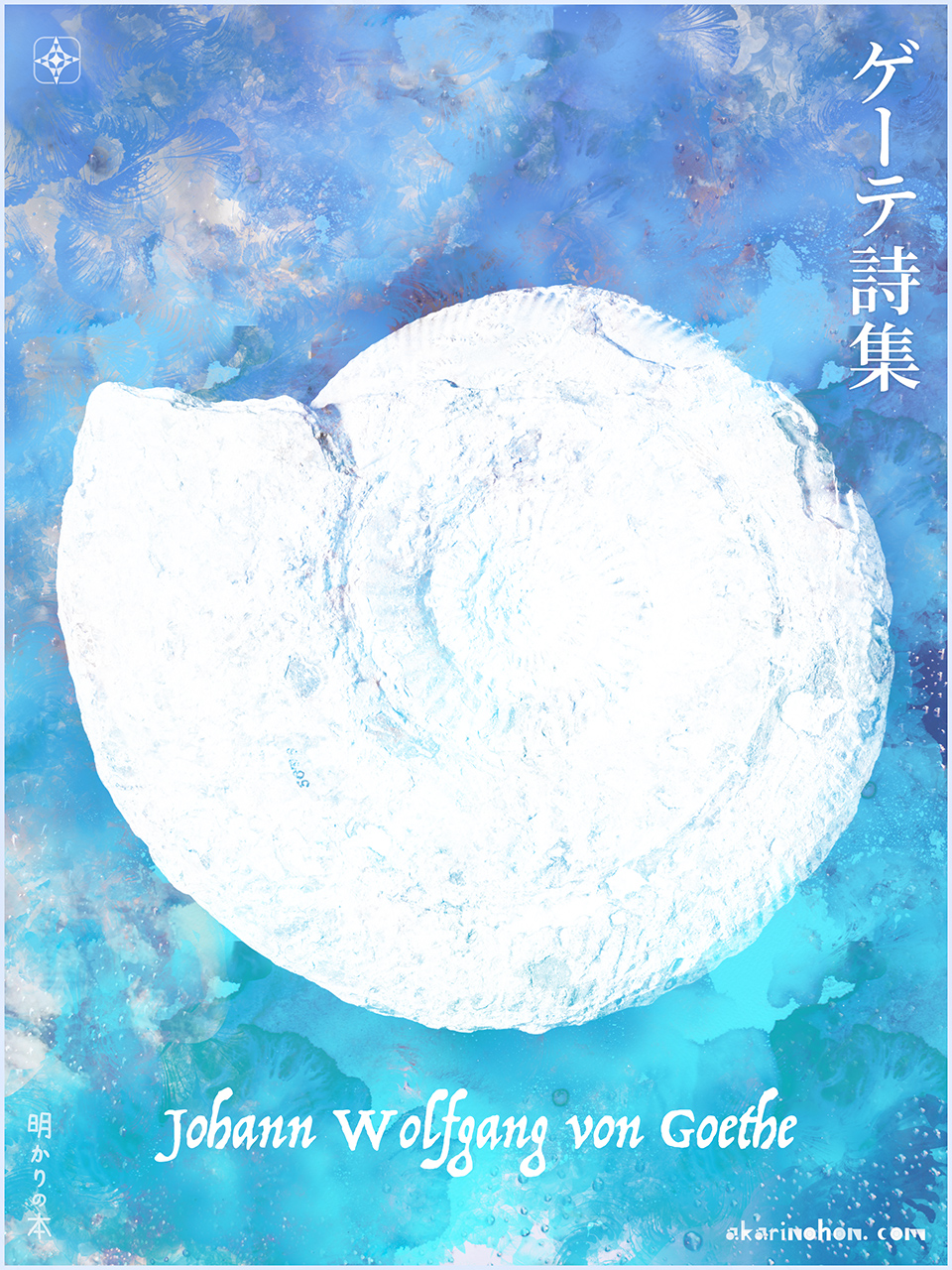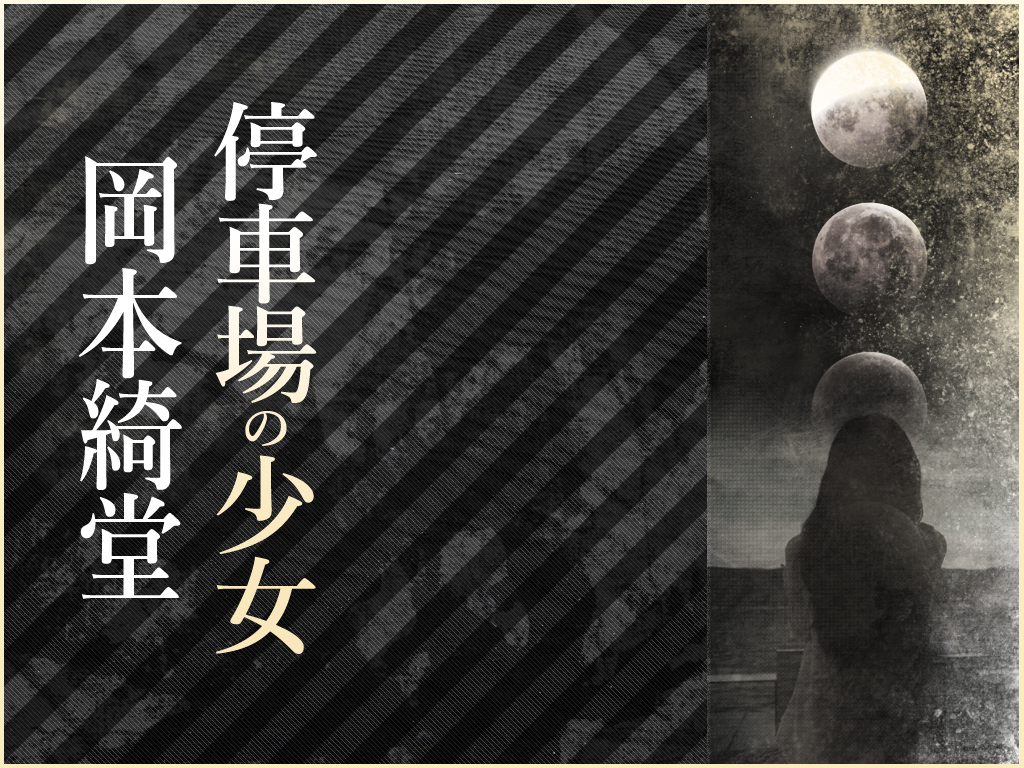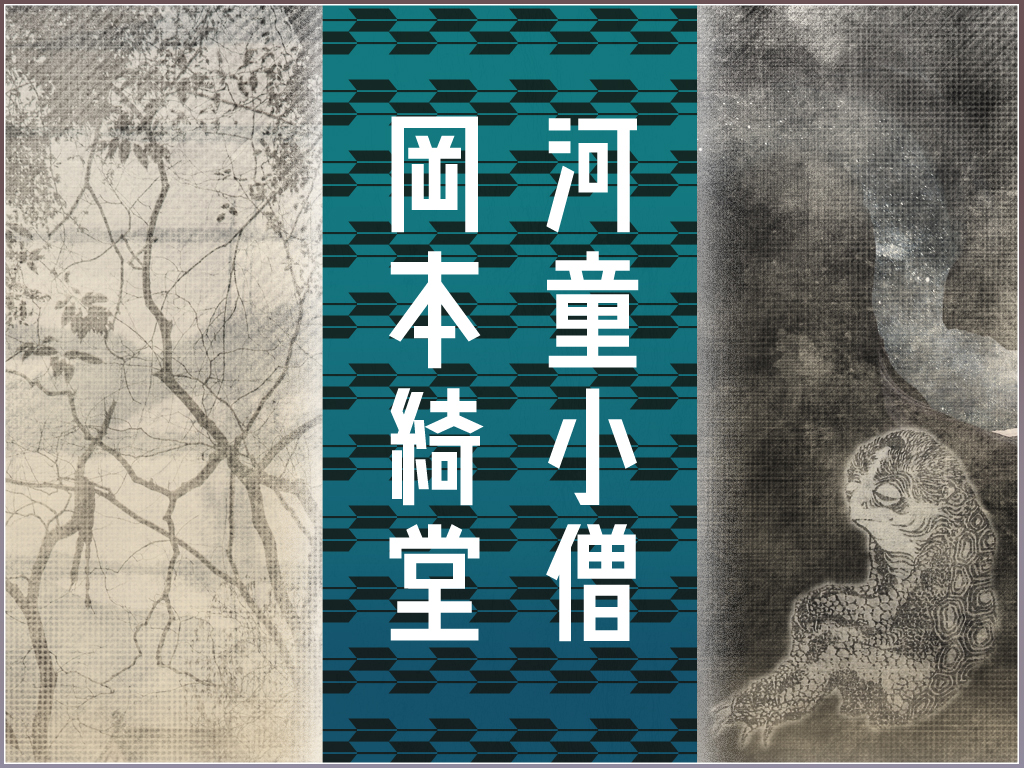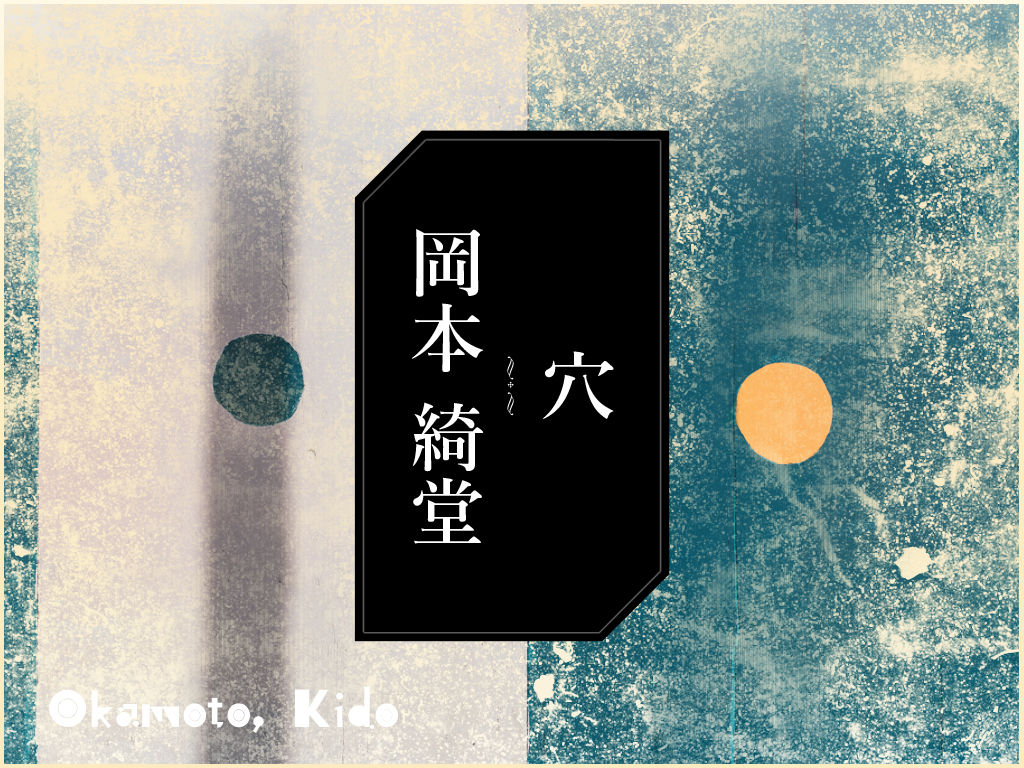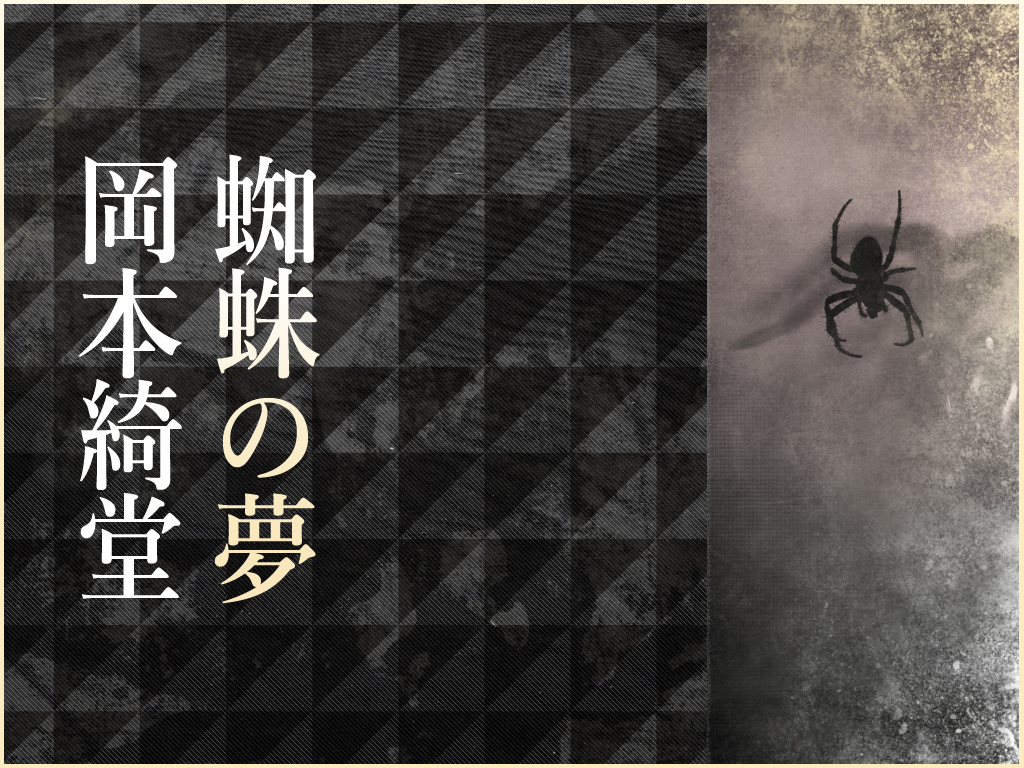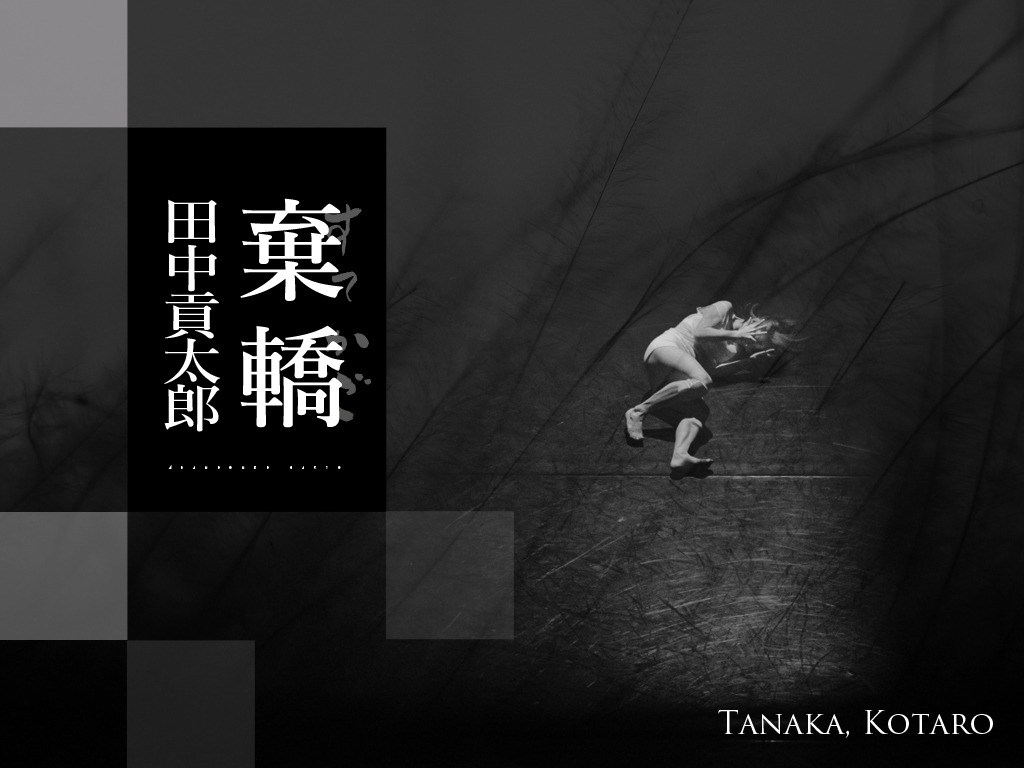今日は岡本綺堂の「影を踏まれた女」を公開します。縦書き表示で全文読めますよ。
これは子どもの遊びを発端としてはじまる、奇妙な怪異を描いた作品なんですけど……ぼくはフォートナイトというゲームをするのがどうも好きで、今日は近代の子どものやるゲームから、はじまった物語を読んでみました。
普通の生活なら10年に1回くらいしか起きないような珍事が、オンラインのゲームの中ではしょっちゅう起きるのが楽しくって、その失敗をリカバリーする工夫をいろいろ凝らすのが、おもしろいのだ、と思っていたのですが、それは近代の原始的なゲームでもやっぱり、現実にはめったに起きないような事態が生滅し、それがさらに不思議な出来事につながってゆく……。岡本綺堂の怪談は、明治時代からさらに古い時代へ目を向けるという方法で、いま現代で起きている不気味なことの、ひとつの骨組みも示唆しているように思えました。
おせき、という少女が、子どもたちの奇妙なゲームに巻きこまれて、さらに都市伝説のような迷信を信じてしまうことから……つづきは本文をごらんください。子どもの頃に、影を踏む、影を踏まれる、という遊びはたしかにやったことがあるなあと思いました。あと新品の靴を、好きな子に踏んでもらうのが楽しかった、という記憶があります。
今回は嘉永二年(1849年)のことを書いていて、調べてみると岡本綺堂は、おおよそ60年前の怪談を書いたことになります。今の時代からいうと170年前の物語です。
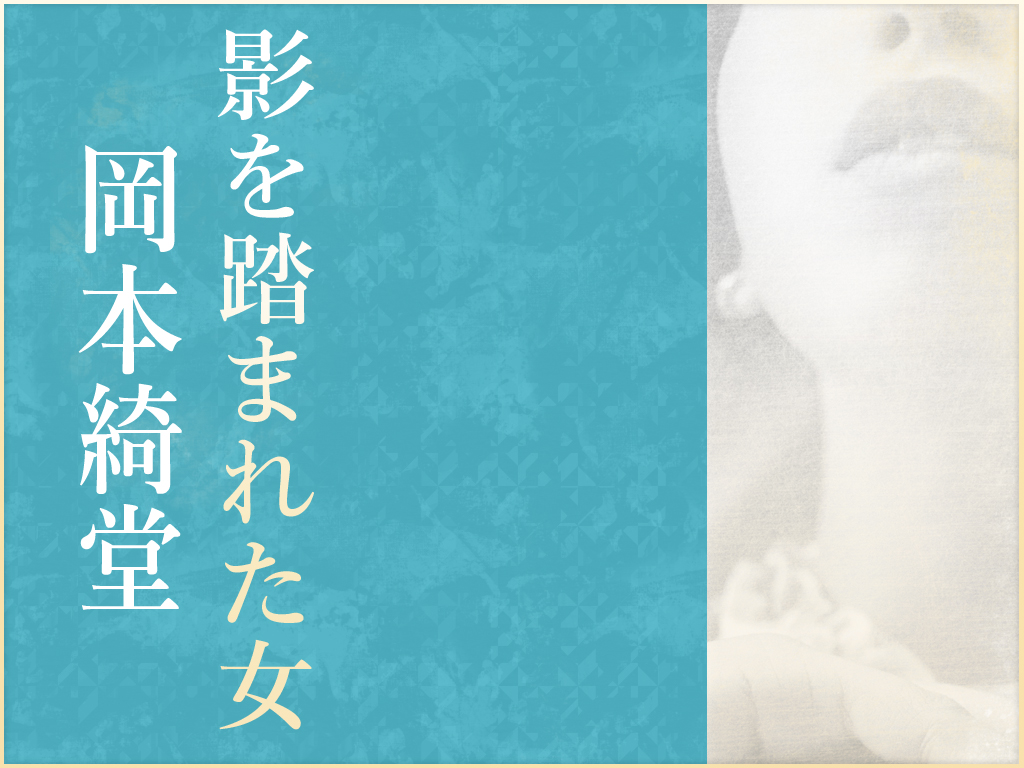
以下の「シンプル表示の縦書きテキスト」をご利用ください。(縦書きブラウザの使い方はこちら)
https://akarinohon.com/migration/kageo_fumareta_onna.html
(約10頁 / ロード時間約30秒)
★シンプル表示の縦書きテキストはこちら
明かりの本は新サイトに移行しました!
URLの登録変更をよろしくお願いいたします。
明かりの本 新サイトURL
https://akarinohon.com
(Windowsでも、なめらかな縦書き表示になるように改善しました!)
appleのmacやタブレットやスマートフォンなど、これまで縦書き表示がむずかしかった端末でも、ほぼ99%縦書き表示に対応し、よみやすいページ構成を実現しました。ぜひ新しいサイトで読書をお楽しみください。
ここからは新サイトの「ゲーテ詩集」を紹介します。縦書き表示で読めますよ。
幼かった頃の夢想のことを、ゲーテは「黄金の空想よ」と記します。ゲーテの詩には、神話的なものと理知的なものが混在していて、これが魅力のように思います。ゲーテはゲルマン神話と、とくにギリシャ神話の影響が色濃いようです。
この詩集は生田春月が翻訳をした作品です。ゲーテは政治家としても活躍し、かのナポレオンからも尊敬されていた作家で、その言葉を詩で楽しめるというのは、なんだか嬉しいように思います。
(総ページ数/約10頁 ロード時間/約10秒)
『ゲーテ詩集』全文を読むにはこちらをクリックしてください
・top page ・本屋map ・図書館link ★おすすめ本 ★書籍&グッズ購入