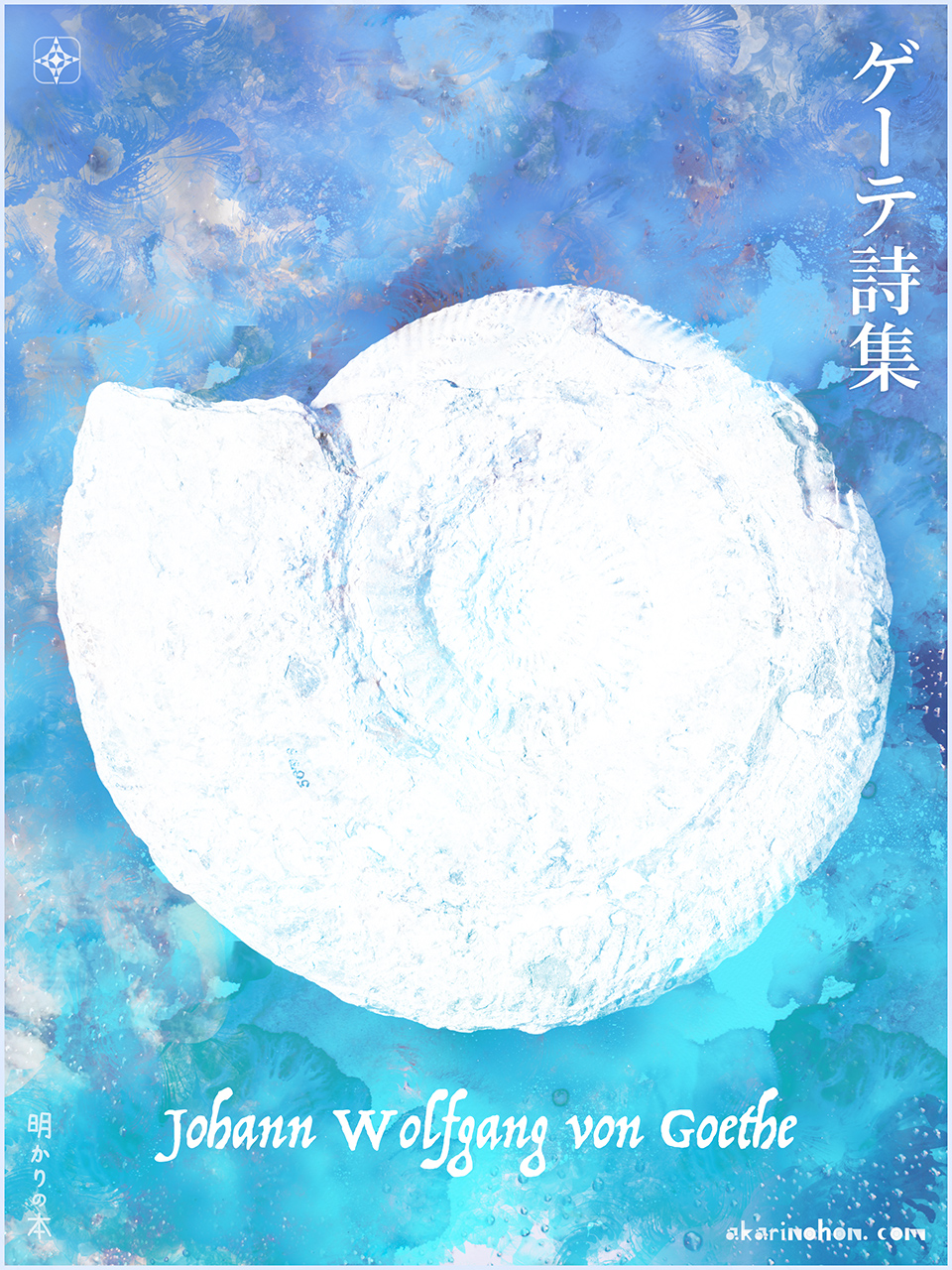お気に入りに追加
お気に入りに追加
今日は柳田國男の「こども風土記」その19を公開します。縦書き表示で全文読めますよ。
今回、ちょっと興味深いことが書いてあって、ふつうはいわないような悪口を、正月のめでたい時期に、子どもにいわせるという、奇妙な祝い方があった。
悪戯の意味もあったし、(柳田はそう述べていないわけですが)きっとハレとケガレの差異をつける意図もあっただろうし、免疫として機能することもあっただろうし、なんだか不思議だけどおもしろい習わしだなと思いました。
ヨンドリ棒を持った子どもが、このトリックスター役を担っていた。
柳田國男の民俗学を、現代の学問で解き明かすという活動をめったに見たことが無いんですけど、いっぽうで柳田國男の民俗学からヒントを得て現代の物語が編み出されるのはこれは、今もすごくよく行われていると思うんです。そうなる理由みたいなのが、どうも読んでいて明らかになってくるんですけど、柳田は、学問で扱えないような、曖昧模糊とした領域に突っ込んでゆくんですよ。真偽のほどが定かにしようがない、これは事実だと決定づけられない、どうにも判断がつけられないところを、柳田國男が切ってゆくんです。読んでいてとっても楽しいんですけど、これは事実を追及した学問というよりも、民話と空想の入り混じった物語のように思えてきます。
昔話として読むと、すこぶるおもしろいです。事実なのかどうかは、ぼくにはまったく判断つかないです。
ゆの木の下のおん事は
さればその事めでとう候
さればその事めでとう候
1月1日の年始めに、子どもたちがこういうことを言った村々があったと言うんですよ。現代では誰も言わないし、その意味もほとんど誰も知らない。ことばが消えてしまったのだ、と思いました。
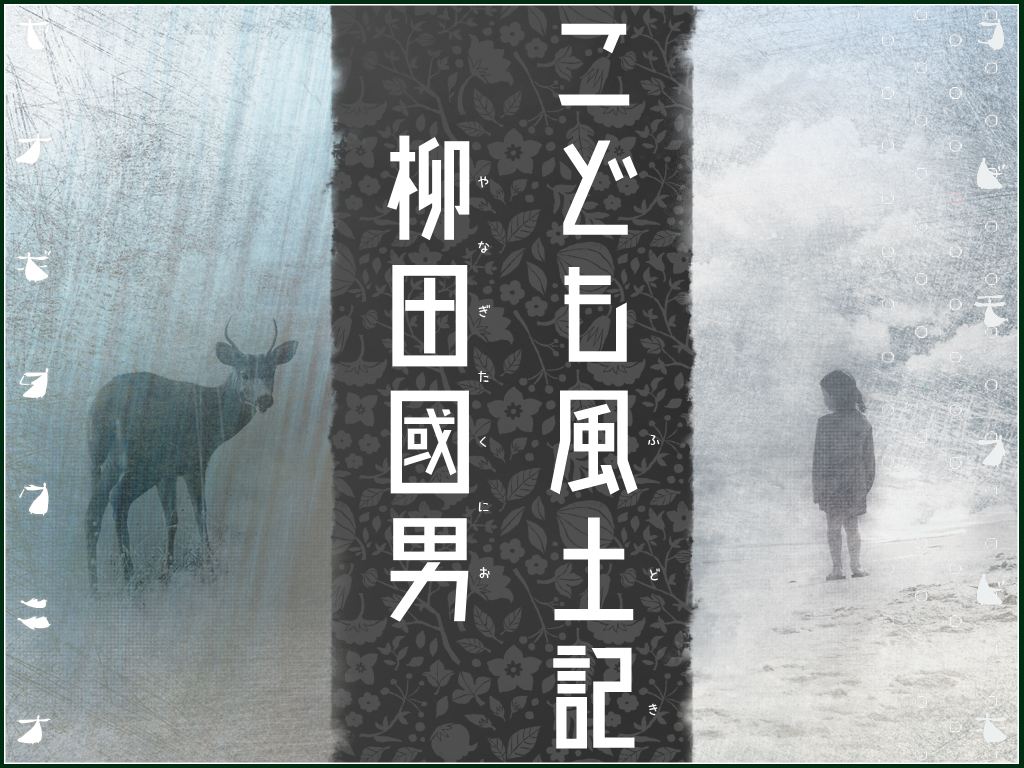
以下の「シンプル表示の縦書きテキスト」をご利用ください。(縦書きブラウザの使い方はこちら)
https://akarinohon.com/migration/kodomo_fudoki19.html
(約5頁 / ロード時間約30秒)
★シンプル表示の縦書きテキストはこちら
横書きはこっち
明かりの本は新サイトに移行しました!
URLの登録変更をよろしくお願いいたします。
明かりの本 新サイトURL
https://akarinohon.com
(Windowsでも、なめらかな縦書き表示になるように改善しました!)
appleのmacやタブレットやスマートフォンなど、これまで縦書き表示がむずかしかった端末でも、ほぼ99%縦書き表示に対応し、よみやすいページ構成を実現しました。ぜひ新しいサイトで読書をお楽しみください。
ここからは新サイトの「ゲーテ詩集」を紹介します。縦書き表示で読めますよ。
幼かった頃の夢想のことを、ゲーテは「黄金の空想よ」と記します。ゲーテの詩には、神話的なものと理知的なものが混在していて、これが魅力のように思います。ゲーテはゲルマン神話と、とくにギリシャ神話の影響が色濃いようです。
この詩集は生田春月が翻訳をした作品です。ゲーテは政治家としても活躍し、かのナポレオンからも尊敬されていた作家で、その言葉を詩で楽しめるというのは、なんだか嬉しいように思います。
装画をクリックするか、ここから全文を読んでください。 (使い方はこちら) (無料オーディオブックの解説)
(総ページ数/約10頁 ロード時間/約10秒)
『ゲーテ詩集』全文を読むにはこちらをクリックしてください
・top page ・本屋map ・図書館link ★おすすめ本 ★書籍&グッズ購入
Similar Posts:
- None Found