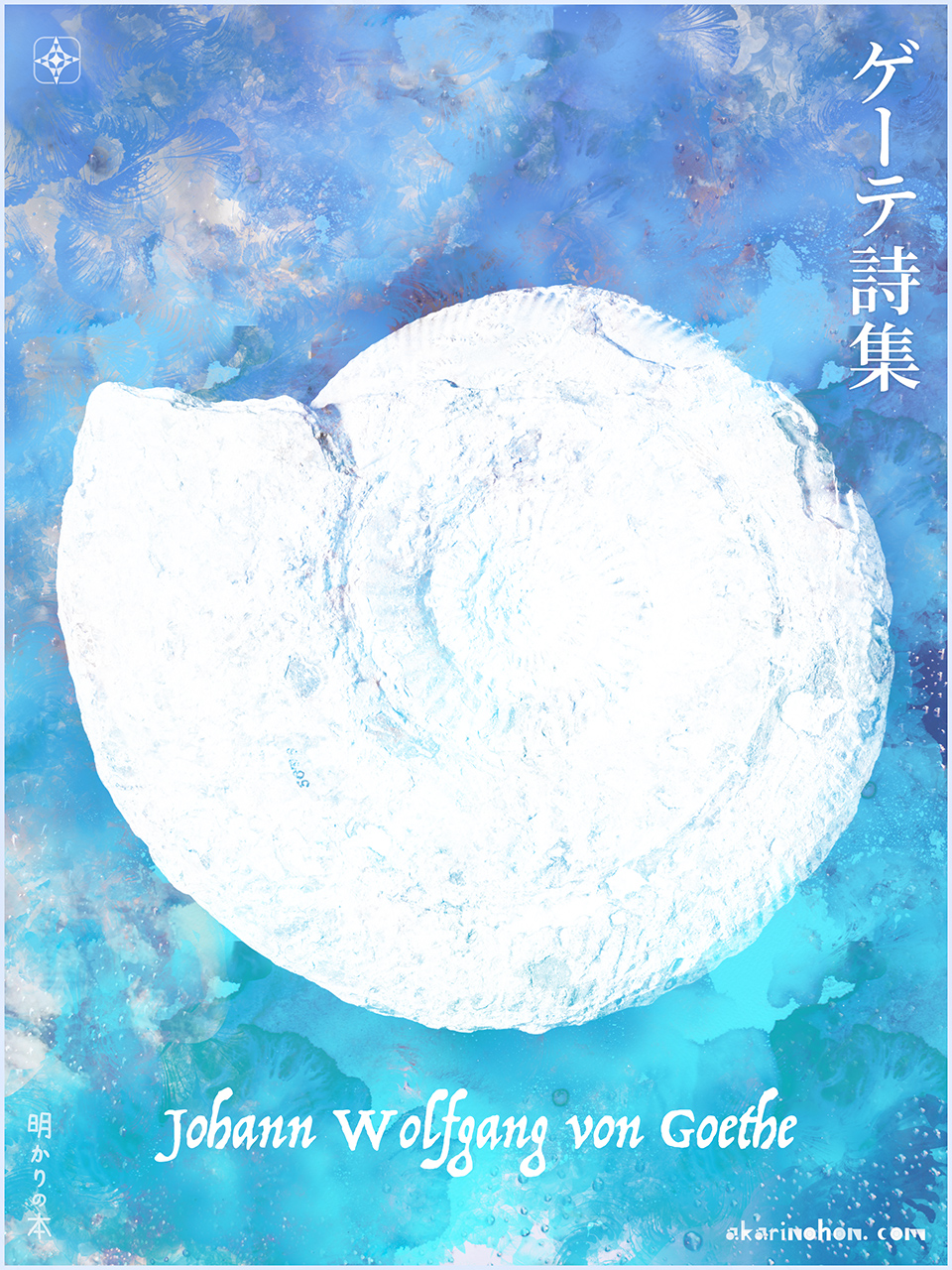お気に入りに追加
お気に入りに追加
今日は夏目漱石の「こころ」その5を公開します。縦書き表示で全文読めますよ。
ここから先生自身が語り手になります。あれっと、おもったんですが、主人公の青年は、先生に逢うためにものすごく重大な旅に出たはずなのに、汽車の中で先生からの長い手紙を読んでみると、もう先生と話すことは出来ないことが明らかになっている。いや、むしろもう逢えないと判ったので、その逢えない現場に行くことにしたことが、明記されています。考えてみれば、逢えるんだったら父の臨終よりも重大なことだと言えると思うんですよ。でも先生がもう居ない東京にほんの短い時間滞在しても、ぜんぜん意味が無いように思えるんです。
先生も本文でこう記しています。「あなたの大事なお父さんの病気をそっち退けにして、何であなたが宅を空けられるものですか。」
青年は先生に逢いたいわけです。先生からの長い手紙を、汽車の中で読んでみると、逢えないことがすでに明らかな手紙だったわけで、手遅れな状況を書いている。あまり誰も気にして読まないと思うんですけど、これなんかすごく妙だなと思いました。
妙と言えば、夏目漱石と正岡子規の関係もすこぶる妙ですよ。現代人から見れば、漱石こそが文学の中心に居るわけですけど、生前の正岡子規は、漱石の小説を1回たりとも読んだことが無い。子規が亡くなったというので、その弔いの意味も込めて漱石は、子規の創刊した文芸誌「ホトトギス」に処女作の猫の小説を書いて載せて、読者を賑わせて、子規の「ホトトギス」という文芸誌の存在をのちへと繋げた。でも正岡子規はそういう未来になることを、知らんわけです。親友が著名な作家になることを、期待はしていたかもしれないですけど。
汽車に乗っている青年の状況はすこぶる妙なんですけど、漱石の文学人生と深く共鳴しているように思えるんです。
この先生の長い遺書を読んでいる状況が、前回の最終ページ(中巻 最終ページ)に記されています。本文、こうです。
父ははっきり「有難う」といった。父の精神は存外朦朧としていなかった。
私はまた病室を退いて自分の部屋に帰った。そこで時計を見ながら、汽車の発着表を調べた。私は突然立って帯を締め直して、袂の中へ先生の手紙を投げ込んだ。それから勝手口から表へ出た。私は夢中で医者の家へ馳け込んだ。私は医者から父がもう二、三日保つだろうか、そこのところを判然聞こうとした。注射でも何でもして、保たしてくれと頼もうとした。医者は生憎留守であった。私には凝として彼の帰るのを待ち受ける時間がなかった。心の落ち付きもなかった。私はすぐ俥を停車場へ急がせた。
私は停車場の壁へ紙片を宛てがって、その上から鉛筆で母と兄あてで手紙を書いた。手紙はごく簡単なものであったが、断らないで走るよりまだ増しだろうと思って、それを急いで宅へ届けるように車夫に頼んだ。そうして思い切った勢いで東京行きの汽車に飛び乗ってしまった。私はごうごう鳴る三等列車の中で、また袂から先生の手紙を出して、ようやく始めからしまいまで眼を通した。
青年は、もう東京に辿りつくつもりで居ますよ。しかし辿りついても……どうにもならないですよ。父の臨終に立ち会うためにふたたび田舎へ戻らねばならないですし、母を裏切るわけにもいかないですし、東京に入っちゃったら、二重の苦悩を背負うことになる。自分だったら途中で引き返しますよ。
こりゃもう他人の自分にはどうにもならないというんで、東京に行くのを辞めて、汽車をいったん降りて田舎に帰ります。漱石はしかし、そういうところは明記せずに、というかそれでも東京に行くのがこの青年の心情なのかもしれないです。それで漱石は、こんどは先生がどうして挫折したのか、それをどんどん書き記すんです。
先生も変なんです。もう気力もなにもかも無くなって、すべてを終わらせることにした人が、こんなに細部まで気を配った周到な手紙を書くわけが無い。よく、漱石は現実社会とは異なる、小説らしい小説空間を描きだした作家だと言われますが、ほんとにこんな用意周到な長文の手紙を、絶望した人間が書くわけが無いですよ。とくに今回、漱石は虚構である小説を、事実っぽく書くのはあえて避けています。ありえない構造が3つくらい折り重なっています。そこがなんでしょうか、読んでいて、えーと、源氏物語とか万葉集みたいなこう、余裕のある文学に感じられます。
単に薄っぺらでデタラメなインチキ話とまったく違って、なにかがこう印象深いと感じさせるのは、漱石はそもそも、矛盾した人間性を描きだそうとして、ややこしい状況の人物たちを描いているわけで、状況を検討するとけっこう筋が通っていないわけなんですが、そこを言葉でしっかり捉えているというか、悲しい人の内奥に言葉が存在していないのにたいして、悲劇を創造する劇作家は、その悲しい事態を表現しうる言葉を持っている。言葉が無いところのための言葉が描きだされている。
それで、文章と実際とのあいだに、何重かのレイヤーが張り巡らされることになっているように思うんです。ある構造を表現するために、背景レイヤーと人物レイヤーと社会的事件のレイヤーと、いくつもの階層の表示が必要になってくる。そこが顕著になるのが、この文章だと思いました。本文こうです。
私は何千万といる日本人のうちで、ただあなただけに、私の過去を物語りたいのです。あなたは真面目だから。あなたは真面目に人生そのものから生きた教訓を得たいといったから。
「あなただけに」という、この文を書いているのは、漱石です。漱石の読者は一人では無くてものすごくたくさん居ます。「あなただけに、私の過去を物語りたい」と考えているのは漱石では無くて、架空の人物「先生」です。人生そのものから生きた教訓を得たい、ということは、短文とか文章のみから教訓を得るのでは無くて、現実に居る人間の事実から学びたいということです。文章そのものの持つ単純な意味と、その文全体が指し示している意味が、ものすごく階層分けされて、多重のレイヤー構造になって駆動している。
いっぽうで、この文章は、漱石自身の手紙そのものにも近い、平易な文章とも解釈出来るな、という、スムーズに書き記された箇所もあるんです。本文こうです。
暗いものを凝と見詰めて、その中からあなたの参考になるものをお攫みなさい。
これは漱石が、漱石の読者に、そのまんまの意味で書いているようにも思えます。物語を駆動させるための多重レイヤー化された箇所もあれば、漱石の現実の手紙とさして変わらないような一文もあって、それが美しく混じりあっているのが、漱石の文学なのではないかと思いました。
小説の構造は、作者→架空の語り手→架空の世界→想像上の読者像→現実の読者と、3階層か5階層くらいから成り立っていると思うんですが、今回の「こころ」では、この「語り手」と「想像上の読者像」ががっちりと人格づけられていて、ここが印象深いように思いました。「私」や「あなた」という記述に肉体が備わっているのが、独自で強固な物語になっているように思います。
この文章が印象に残りました。
私はたった一人山へ行って、父母の墓の前に跪きました。半は哀悼の意味、半は感謝の心持で跪いたのです。そうして私の未来の幸福が、この冷たい石の下に横たわる彼らの手にまだ握られてでもいるような気分で、私の運命を守るべく彼らに祈りました。あなたは笑うかもしれない。私も笑われても仕方がないと思います。しかし私はそうした人間だったのです。
「先生」は、両親の家を上手く継げないどころか、財産も受け取れない状況に陥り、二度と故郷に帰らない決心で、すべてのものを手放して、東京だけで生きることに決め、そのため奇妙な下宿に住むことになった、その過去について手紙で詳細に記すのでした。
ひどい不幸というのがあって、そこからなんとか這いだして、その後遺症のような不都合として、プライベート空間がガッチリ守られているような、満足のゆく住み家に住むことなど、できない。そのため男2人の友人同士そして若い女1人、この3人の危機的な△関係を形成することになる……。現代でもかならず起きそうな状況を、漱石は描きだしたんだなあと思いました。
物語はこのように展開します。本文こうです。
私は未亡人に会って来意を告げました。未亡人は私の身元やら学校やら専門やらについて色々質問しました。そうしてこれなら大丈夫だというところをどこかに握ったのでしょう、いつでも引っ越して来て差支えないという挨拶を即坐に与えてくれました。
…………
……時々は彼らに対して気の毒だと思うほど、私は油断のない注意を彼らの上に注いでいたのです。おれは物を偸まない巾着切みたようなものだ、私はこう考えて、自分が厭になる事さえあったのです。
あなたは定めて変に思うでしょう。その私がそこのお嬢さんをどうして好く余裕をもっているか。そのお嬢さんの下手な活花を、どうして嬉しがって眺める余裕があるか。同じく下手なその人の琴をどうして喜んで聞く余裕があるか。そう質問された時、私はただ両方とも事実であったのだから、事実としてあなたに教えて上げるというより外に仕方がないのです。
ヒロインの呼び名が少しずつ変化して、それと同時にお互いが打ち解けてゆくんですけど、この繊細な呼び名の変転に、なんだか魅了されました。
それで、不吉な友人Kが登場するわけなんですけど、kは坊さんの家からやってきた学生なんですが、なぜKと書いたのか。Kは何者なのか、調べていたんですけど、同時代に活躍した文学者にカフカが居て、カフカはいつもKという名前を使ったんです。カフカの作品を漱石は絶対に読んでいないわけですけど、そういう表記法を、漱石が西洋文学や西洋文化を見ているときに、どうも学んだというか、Kという文字を気に入ったようなんです。というのも、ある西洋の文学者の小さな博物館のようなところを夏目漱石が訪れたとき、ゲストブックに K と記入していったという記録が残っているんです。Kって漱石とまったく似ていないんですけど、ただ名前はじつは、漱石の本名の K からどうもとったようなんですよ。こころの K は漱石とあらゆる意味で似ていないです。でも、名前は漱石の英国滞在中のプライベートの名前 K と同じなんです。漱石はイギリスで絶望して学校に行かなくなったわけで、そのときの名前は夏目漱石では無く、ただKだった。そのKと「私」とが同じ下宿に住みはじめた……。本文こうです。
Kと私も二人で同じ間にいました。山で生捕られた動物が、檻の中で抱き合いながら、外を睨めるようなものでしたろう。二人は東京と東京の人を畏れました。それでいて六畳の間の中では、天下を睥睨するような事をいっていたのです。

以下の「シンプル表示の縦書きテキスト」をご利用ください。(縦書きブラウザの使い方はこちら)
https://akarinohon.com/migration/kokoro05.html
(約100頁 / ロード時間約30秒)
★シンプル表示の縦書きテキストはこちら
横書きはこっち
明かりの本は新サイトに移行しました!
URLの登録変更をよろしくお願いいたします。
明かりの本 新サイトURL
https://akarinohon.com
(Windowsでも、なめらかな縦書き表示になるように改善しました!)
appleのmacやタブレットやスマートフォンなど、これまで縦書き表示がむずかしかった端末でも、ほぼ99%縦書き表示に対応し、よみやすいページ構成を実現しました。ぜひ新しいサイトで読書をお楽しみください。
ここからは新サイトの「ゲーテ詩集」を紹介します。縦書き表示で読めますよ。
幼かった頃の夢想のことを、ゲーテは「黄金の空想よ」と記します。ゲーテの詩には、神話的なものと理知的なものが混在していて、これが魅力のように思います。ゲーテはゲルマン神話と、とくにギリシャ神話の影響が色濃いようです。
この詩集は生田春月が翻訳をした作品です。ゲーテは政治家としても活躍し、かのナポレオンからも尊敬されていた作家で、その言葉を詩で楽しめるというのは、なんだか嬉しいように思います。
(総ページ数/約10頁 ロード時間/約10秒)
『ゲーテ詩集』全文を読むにはこちらをクリックしてください
・top page ・本屋map ・図書館link ★おすすめ本 ★書籍&グッズ購入
Similar Posts:
- None Found