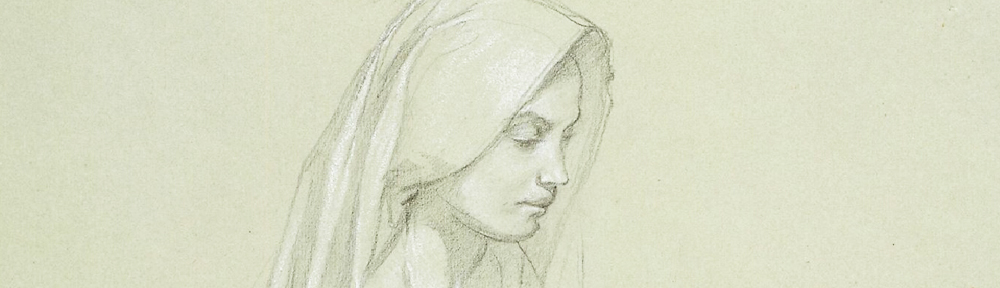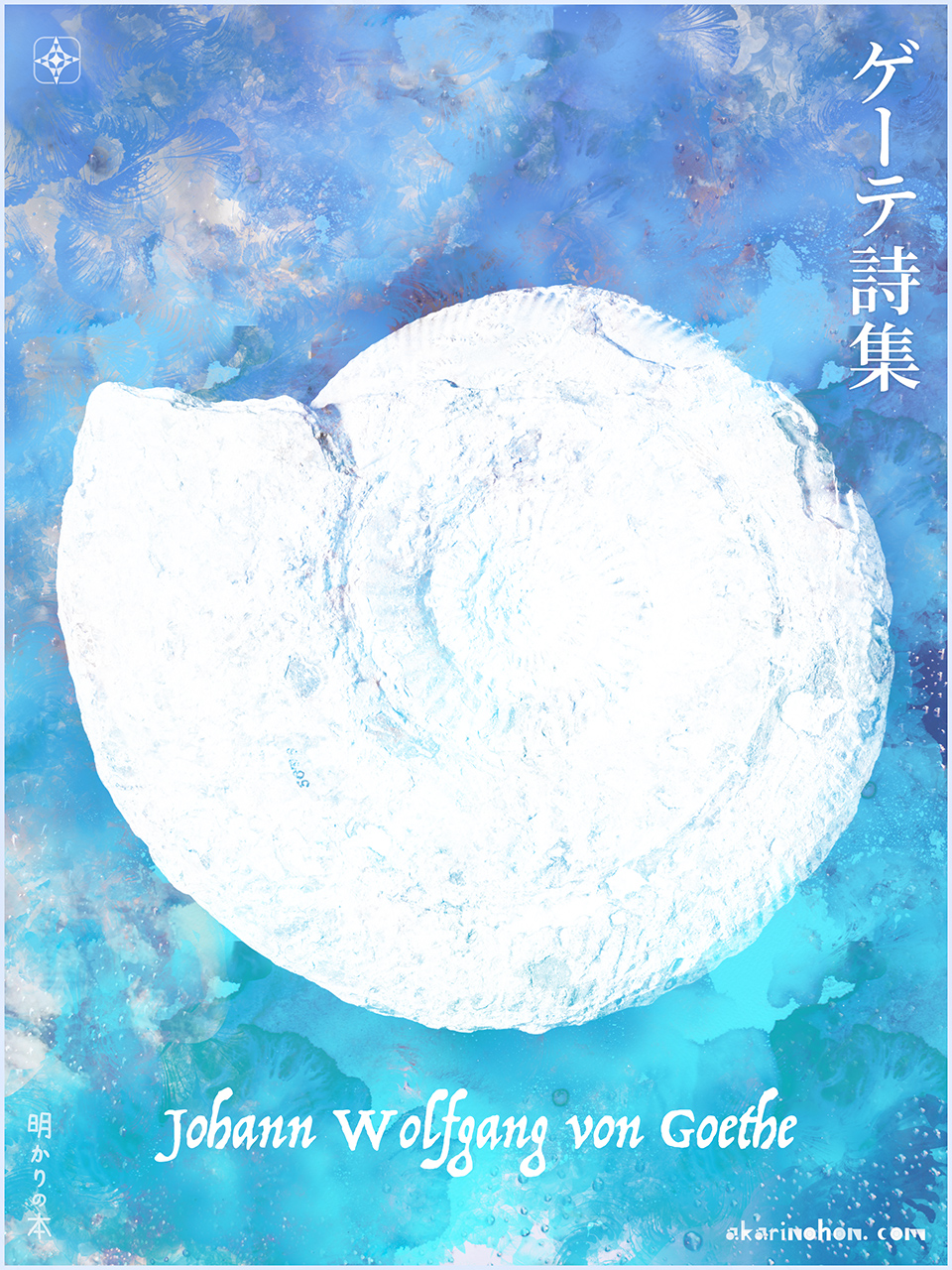お気に入りに追加
お気に入りに追加
今日は坂口安吾の「枯淡の風格を排す」を公開します。縦書き表示で全文読めますよ。
坂口安吾は、戦争中でさえ、自分の生きたいように生きられた唯一の作家という感じがするんですけど、その安吾がどうやって己の自由を確保しえたかというのが、今回の随筆でちょっとだけ見えたように思いました。
安吾は、「枯淡」や「さび」の精神を批判するんです。そこでは自己批判が機能しない。「他人に許されるために他を許さうとする、かういふ子供同志の馴れ合ひのやうな無邪気な道徳律が」阿保らしくてイカンぞと安吾は言うんです。それよりも「悩む者の蒼ざめた悲しさ」のほうを安吾は重大視する。「悩むべきものに悩むまいとする逃避的な」態度が枯淡を求める心の中にあると言うんです。
安吾のいう「肉体をもたない悩みはまことの悩みではない。」というのがすごく印象に残ったんですけど、安吾の批判するその「まことに地についた肉の悩み」の実際を、もう少しこう、ちゃんと読み解けたら良いのになあと思いました。他人の忖度ばかりをしてしまうような、弱々しい優しさを持つ文学青年を、鼓舞するような安吾の言葉を読んでいて、この人は当時すごい先生だったんだろうなと感じました。
「架空なパラドックスを弄し」てはならん、という安吾の言葉を読んで、ウィトゲンシュタインの哲学批判のことを連想しました。ウィトゲンシュタインによれば、思考の限界を超えた言説によって、思惟の谷間に落ちてしまった者へ、元の生き方に戻るためのハシゴを用意することが、哲学にとってもっとも重大なんです。
安吾は随筆や評論がじつにみごとなんですが、小説創作はどうも上手くないんですよ。それについて安吾当人も「自分の小説の下手糞なのも打ち忘れて、(徳田秋声氏の小説に)腹が立つてくる」とか書いています。文学論も記されていて、小説の会話には、語られないものごとの秘められていることこそが肝要であって、会話の立体性こそ重大だと言うんですけど、まさに言い得て妙で、あのノーベル文学賞カズオイシグロの「わたしを離さないで」という小説は、なんだか安吾が強烈に求めている文学を完全に実現してしまっている、と思いました。安吾はジッドこそが「作家の本当」である、と今回書いています。
安吾はこう書きます。
人間生きるから死ぬまで持つて生れた身体が一つである以上は、せいぜい自分一人のためにのみ、慾ばつた生き方をすべきである。毒々しいまでの徹底したエゴイズムからでなかつたら、立派な何物が生れやう。
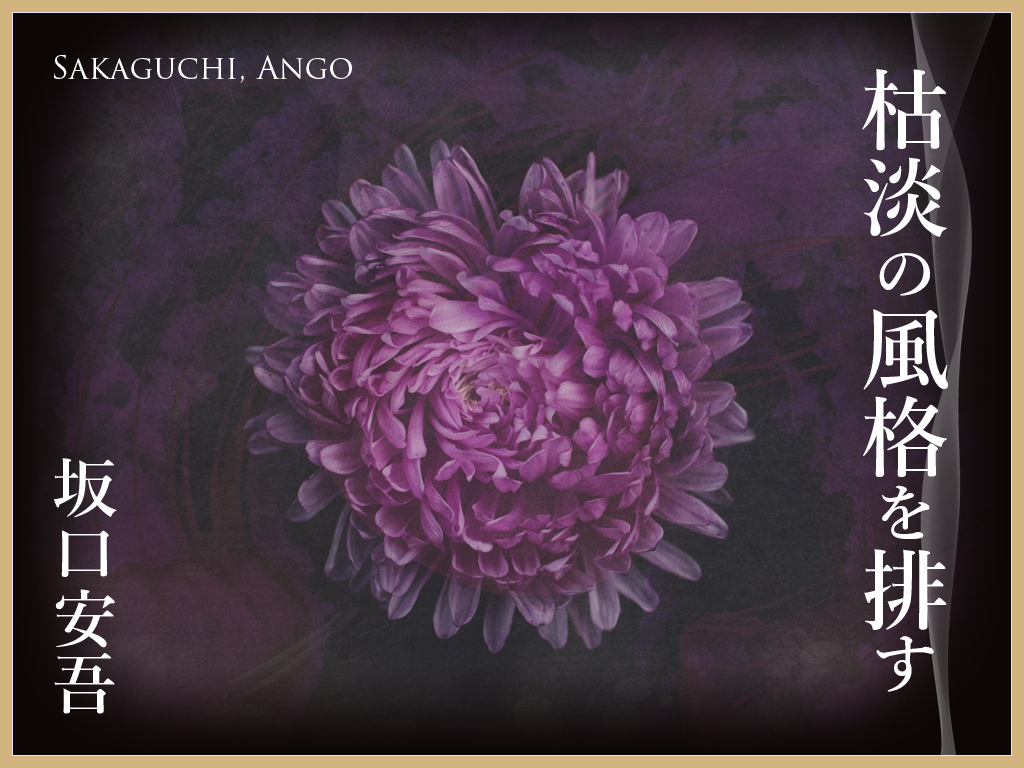
以下の「シンプル表示の縦書きテキスト」をご利用ください。(縦書きブラウザの使い方はこちら)
https://akarinohon.com/migration/kotanno_fukakuo_haisu.html
(約10頁 / ロード時間約30秒)
★シンプル表示の縦書きテキストはこちら
明かりの本は新サイトに移行しました!
URLの登録変更をよろしくお願いいたします。
明かりの本 新サイトURL
https://akarinohon.com
(Windowsでも、なめらかな縦書き表示になるように改善しました!)
appleのmacやタブレットやスマートフォンなど、これまで縦書き表示がむずかしかった端末でも、ほぼ99%縦書き表示に対応し、よみやすいページ構成を実現しました。ぜひ新しいサイトで読書をお楽しみください。
ここからは新サイトの「ゲーテ詩集」を紹介します。縦書き表示で読めますよ。
幼かった頃の夢想のことを、ゲーテは「黄金の空想よ」と記します。ゲーテの詩には、神話的なものと理知的なものが混在していて、これが魅力のように思います。ゲーテはゲルマン神話と、とくにギリシャ神話の影響が色濃いようです。
この詩集は生田春月が翻訳をした作品です。ゲーテは政治家としても活躍し、かのナポレオンからも尊敬されていた作家で、その言葉を詩で楽しめるというのは、なんだか嬉しいように思います。
(総ページ数/約10頁 ロード時間/約10秒)
『ゲーテ詩集』全文を読むにはこちらをクリックしてください
・top page ・本屋map ・図書館link ★おすすめ本 ★書籍&グッズ購入
Similar Posts:
- None Found