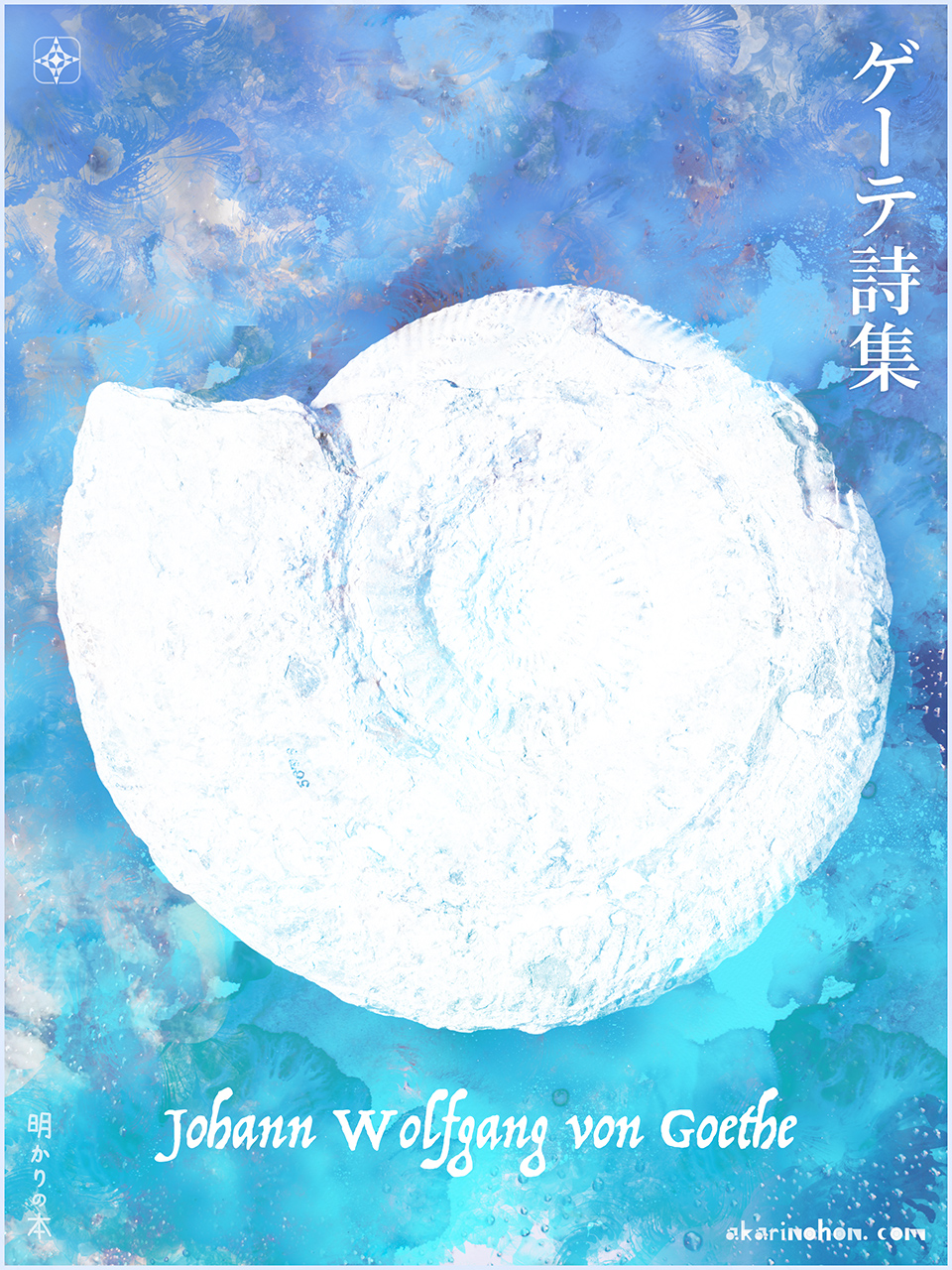お気に入りに追加
お気に入りに追加
今日は柳田國男の「こども風土記」その2を公開します。縦書き表示で全文読めますよ。
子どもの遊びはじつは、世界中を見ても共通するところがあるのだ、と柳田國男が言うんです。えっ? そうだったのかと驚きました。本文こうです。
一人の子が目隠しをして立っていると、その後にいる別の子が、ある簡単な文句で拍子をとって背なかを叩きその手で何本かの指を出して、その数を目隠しの子に当てさせる。
「いかに 多くの 角を 牡鹿が 持つか」という幼子たちのゲームが、世界中にある。背中で起きている出来事を当てるからヒントはまったく無いわけで、ただ運に頼って1本から5本のうちのどれかを当てるゲームのようです。
地域の壁は意外と存在していないようで、世界中で似た遊びが流行った。でもこういう遊びを現代人がやっているんだろうか、国の壁よりもむしろ時代の壁のほうが、はるかにぶ厚いこともあるんだな、と思いました。
戦前の日本にあるかどうか、というのを柳田國男が調べたわけですが、文献や記憶の中には無かった。それでだれか知っている人は居ないか、と会報で問うてみると、そういう遊びがありました、という投稿を送ってきた人が何人か居た。えっ、でもこれって噂だから証拠は無いかもしれないな、そうか……遊びは証拠が残らない秘密の行為だからこそ遊びなんだ……とか思いつつ、そのゲームのことをイメージしてみたんですが、ぼくが子どもだった頃の20世紀末にも、似た遊びはあったなあと思いました。それは背中に文字を書いて、何を書いたか当てるゲームで、この場合は背中の触感で判断できてかなりヒントがあるわけで、笑える言葉を書いたり、ないしょのはなしを伝えるゲームだったり、これはたぶんかなりの子どもがやる遊びだと思いました。
ところで日本大百科全書に、このゲームのルールの詳細が掲載されています。辞書によれば、じつは明治時代に輸入された遊びの可能性が高い。昭和初期にはこういう遊びは消え去ってしまったらしい。
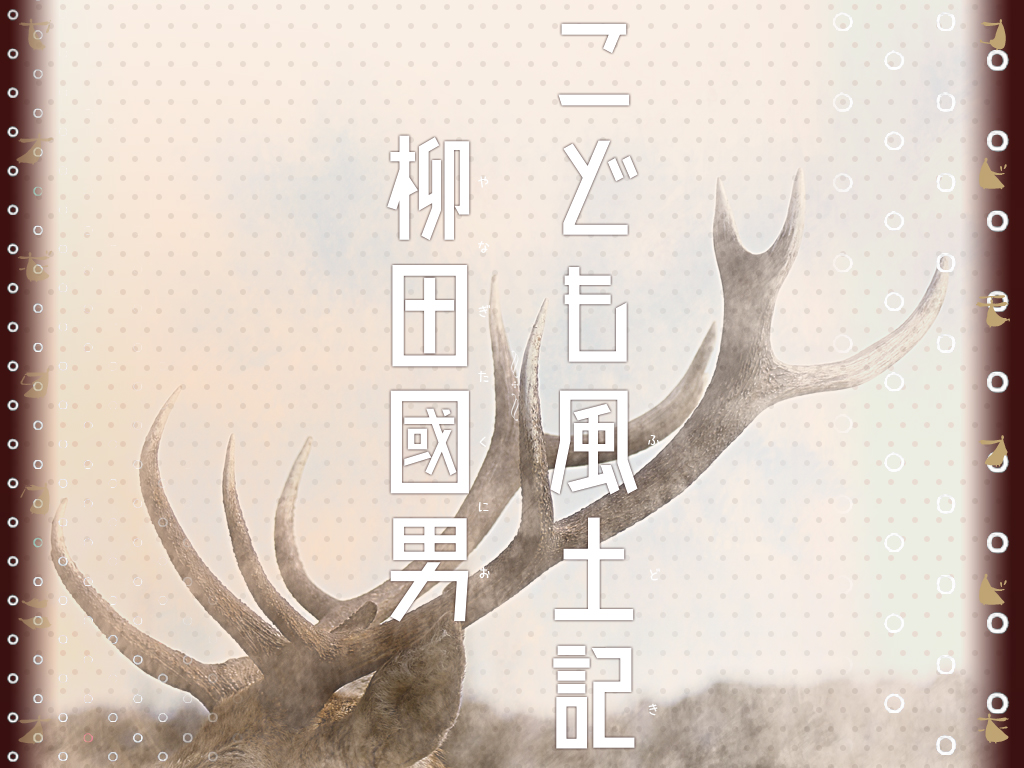
以下の「シンプル表示の縦書きテキスト」をご利用ください。(縦書きブラウザの使い方はこちら)
https://akarinohon.com/migration/kodomo_fudoki02.html
(約5頁 / ロード時間約30秒)
★シンプル表示の縦書きテキストはこちら
横書きはこっち
明かりの本は新サイトに移行しました!
URLの登録変更をよろしくお願いいたします。
明かりの本 新サイトURL
https://akarinohon.com
(Windowsでも、なめらかな縦書き表示になるように改善しました!)
appleのmacやタブレットやスマートフォンなど、これまで縦書き表示がむずかしかった端末でも、ほぼ99%縦書き表示に対応し、よみやすいページ構成を実現しました。ぜひ新しいサイトで読書をお楽しみください。
ここからは新サイトの「ゲーテ詩集」を紹介します。縦書き表示で読めますよ。
幼かった頃の夢想のことを、ゲーテは「黄金の空想よ」と記します。ゲーテの詩には、神話的なものと理知的なものが混在していて、これが魅力のように思います。ゲーテはゲルマン神話と、とくにギリシャ神話の影響が色濃いようです。
この詩集は生田春月が翻訳をした作品です。ゲーテは政治家としても活躍し、かのナポレオンからも尊敬されていた作家で、その言葉を詩で楽しめるというのは、なんだか嬉しいように思います。
装画をクリックするか、ここから全文を読んでください。 (使い方はこちら) (無料オーディオブックの解説)
(総ページ数/約10頁 ロード時間/約10秒)
『ゲーテ詩集』全文を読むにはこちらをクリックしてください
・top page ・本屋map ・図書館link ★おすすめ本 ★書籍&グッズ購入
Similar Posts:
- None Found