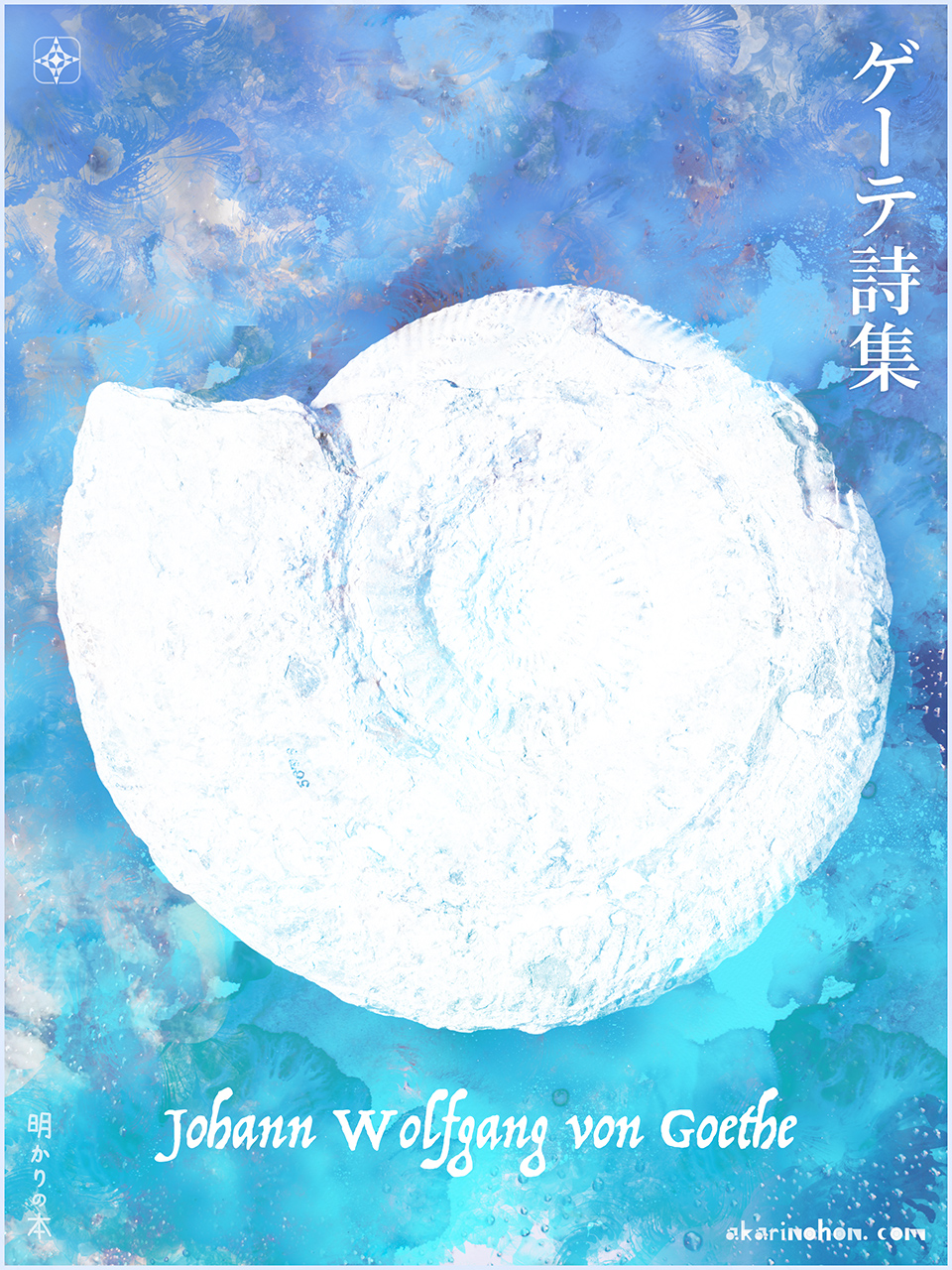お気に入りに追加
お気に入りに追加
今日は夏目漱石の「彼岸過迄(13)松本の話(後編)」を公開します。縦書き表示で全文読めますよ。
いよいよ次の第14回で物語が完結します。今回が実質的には最後の章なんです。これから彼岸過迄を読み終える予定の方は、やはり以下の文章は読まないほうが楽しめるかと思います……。ご注意ください。
須永市蔵は、卒業後の旅行に出かけるのも、義理の母を心配している。漱石が、あいまいな状態の青年を描くときにそれを見守る親類のまなざしで「責任」という言葉を書くんです。これが、説得力を感じる言葉に思えました。
須永市蔵という若者に、隠されていた家の事実を教えたわけで、彼のその後に責任を感じていて、心配をしている。旅先から市蔵がハガキをよこしてくると、僕(松本)は妙に安心する。責任があるからどうするのかというと、ただひたすらに見るんです。忘れずに青年につきあって、じっと見てゆく。
旅先から届いた手紙の内容が、なんだかちょっと須永市蔵という若者の言葉というよりも、漱石の言葉になっちゃってるんですよ。一人旅の卒業旅行なのに、朝日新聞の友人を訪ねて接待を受けたりしていて、変に老成している。登場人物の心境を書くというよりかは、漱石のごく普通の心境を、ついうっかり書いちゃってるんじゃなかろうかと思いました。
この手紙に「野趣」という言葉が出て来ます。意味を調べてみたんですが、なんともすてきな言葉でした。
中野重治という作家の随筆に、こういうことが記されているんです。
だいたい僕は世のなかで素樸というものが一番いいものだと思っている。こいつは一番美しくて一番立派だ。こいつは僕を感動させる。こいつさえつかまえればと、そう僕は年中考えている。僕が何か芸術的な仕事をするとすれば、僕はただこいつを目がける。もちろんたいていは目がけるだけだが。…………(中野重治/素樸ということ/ちくま日本文学全集39より)
この中野重治の言っている素朴ということを、漱石も描きだしていたような気がしました。漱石の文章はこうです。
友人は僕を顧みて野趣があると笑いました。僕も笑いました。ただ笑っただけではありません。百年も昔の人に生れたような暢気した心持がしました。僕はこういう心持を御土産に東京へ持って帰りたいと思います
ここから、旅の手紙が幻想的になっていって、なんだか「夢十夜」みたいでおもしろい描写でした。そうして漱石の「こころ」序盤の描写のような場面がはじまる。始まりなのか終わりなのかなんだか判らない、漱石の物語の渦の中心を描きだしているような文学描写でした。
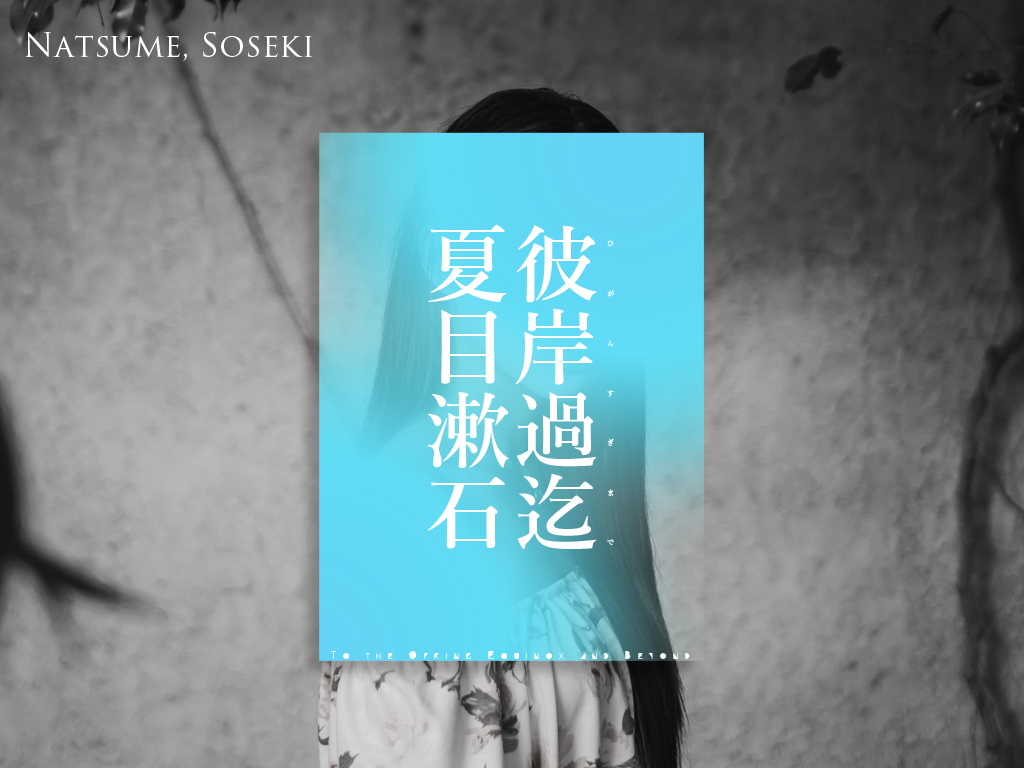
以下の「シンプル表示の縦書きテキスト」をご利用ください。(縦書きブラウザの使い方はこちら)
https://akarinohon.com/migration/higansugimade13.html
(約50頁 / ロード時間約30秒)
★シンプル表示の縦書きテキストはこちら
全文通読はこちら(重いです)
(横書きはこっち)
明かりの本は新サイトに移行しました!
URLの登録変更をよろしくお願いいたします。
明かりの本 新サイトURL
https://akarinohon.com
(Windowsでも、なめらかな縦書き表示になるように改善しました!)
appleのmacやタブレットやスマートフォンなど、これまで縦書き表示がむずかしかった端末でも、ほぼ99%縦書き表示に対応し、よみやすいページ構成を実現しました。ぜひ新しいサイトで読書をお楽しみください。
ここからは新サイトの「ゲーテ詩集」を紹介します。縦書き表示で読めますよ。
幼かった頃の夢想のことを、ゲーテは「黄金の空想よ」と記します。ゲーテの詩には、神話的なものと理知的なものが混在していて、これが魅力のように思います。ゲーテはゲルマン神話と、とくにギリシャ神話の影響が色濃いようです。
この詩集は生田春月が翻訳をした作品です。ゲーテは政治家としても活躍し、かのナポレオンからも尊敬されていた作家で、その言葉を詩で楽しめるというのは、なんだか嬉しいように思います。
(総ページ数/約10頁 ロード時間/約10秒)
『ゲーテ詩集』全文を読むにはこちらをクリックしてください
・top page ・本屋map ・図書館link ★おすすめ本 ★書籍&グッズ購入
Similar Posts:
- None Found