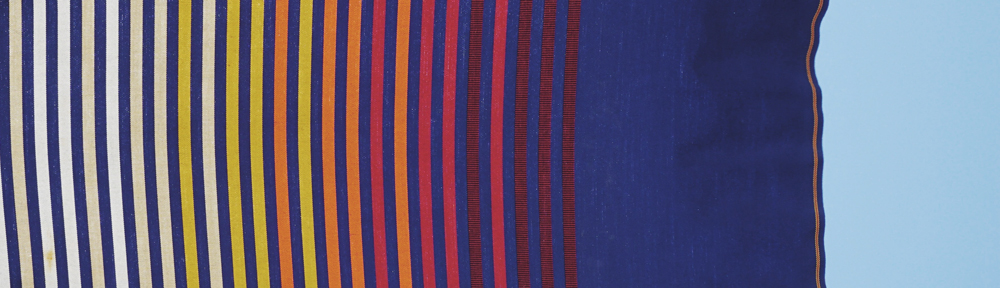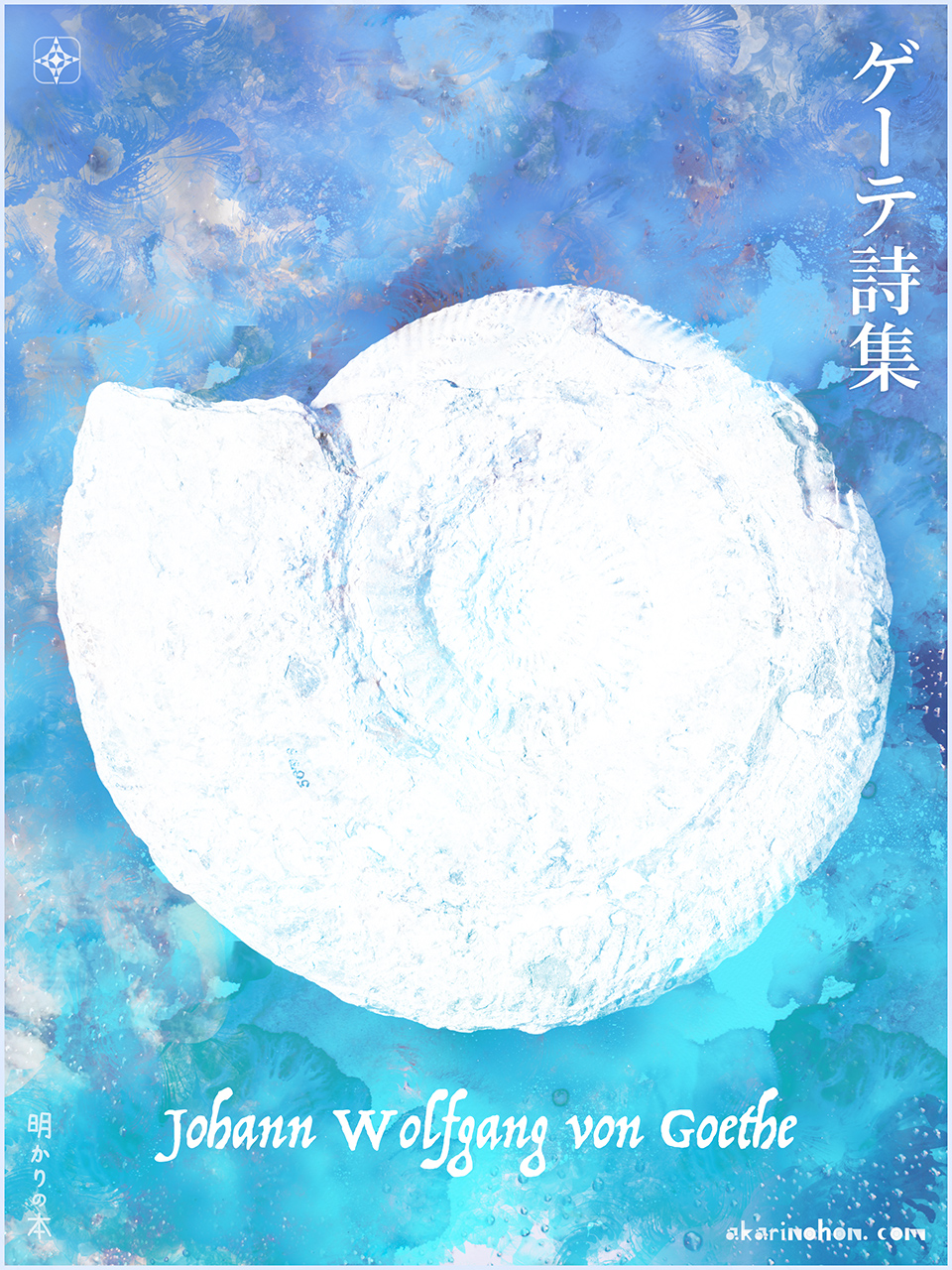今日は夏目漱石の「草枕」その6を公開します。縦書き表示で全文読めますよ。
静まりかえった宿を表現するのに、じつに雅な書き方をしています。人の気配が、自然界の中へ溶け込んでいって消えてしまったような描写です。原文は、こうです。
今日は一層静かである。主人も、娘も、下女も下男も、知らぬ間に、われを残して、立ち退いたかと思われる。立ち退いたとすればただの所へ立ち退きはせぬ。霞の国か、雲の国かであろう。あるいは雲と水が自然に近づいて、舵をとるさえ懶き海の上を、いつ流れたとも心づかぬ間に、白い帆が雲とも水とも見分け難き境に漂い来て、果ては帆みずからが、いずこに己れを雲と水より差別すべきかを苦しむあたりへ――そんな遥かな所へ立ち退いたと思われる。
主人公の画家は、世間についてこう考えています。利害の生じる関係の中で生きていると、恋はうらみを生む。目に見える富は、土くれのようなものだ。名声や賞讃は、こざかしい蜂が生む甘い蜜のように見えて、針を捨て去る蜜のようなものだ。原文はこうです。
利害の綱を渡らねばならぬ身には、事実の恋は讎である。目に見る富は土である。握る名と奪える誉とは、小賢かしき蜂が甘く醸すと見せて、針を棄て去る蜜のごときものであろう。
すぐれた詩人・画家は、モノをとらえるのでは無く、そのモノじたいになる、と男は記しています。胡蝶の夢ではないですが、描かれる対象に、のりうつるというか、それになる。そういう画家が、風景画を描く場合はもう、すごいことになってるなあ、と思いました。宮沢賢治の「ひのきとひなげし」を思い出しました。たしかに漱石が指摘しているように、これはただモノを見て描写しているのでは無くて、あきらかに風景の内部の、そのひとつひとつの生きものへ、すっかりと入りこんでいます。
写実画から宗教画、その後の印象派、それから抽象画から現代美術という展開をした絵画の歴史を、漱石がみごとに捉えていて興味深かったです。漱石は実名をあげずに絵画論を展開しているんですが、パウルクレーの絵画についての、可能性について論じているような気がしました。あ、あと蕪村の絵について書いています。
男は、こういう心境で居ます。「余が心はただ春と共に動いている」旅に出て、ただ良いところで一人ゆっくり休んでいる。そのじつに気持ちがいい、というところを、みごとな詩で、漱石が描いています。興味のある方は、この章だけ読んでみてください。
きれいな女が、同じところをいくたびか通りすぎてゆく。謎めいた描写が美しかったです。

以下の「シンプル表示の縦書きテキスト」をご利用ください。(縦書きブラウザの使い方はこちら)
https://akarinohon.com/migration/kusamakura06.html
(約30頁 / ロード時間約30秒)
★シンプル表示の縦書きテキストはこちら
明かりの本は新サイトに移行しました!
URLの登録変更をよろしくお願いいたします。
明かりの本 新サイトURL
https://akarinohon.com
(Windowsでも、なめらかな縦書き表示になるように改善しました!)
appleのmacやタブレットやスマートフォンなど、これまで縦書き表示がむずかしかった端末でも、ほぼ99%縦書き表示に対応し、よみやすいページ構成を実現しました。ぜひ新しいサイトで読書をお楽しみください。
ここからは新サイトの「ゲーテ詩集」を紹介します。縦書き表示で読めますよ。
幼かった頃の夢想のことを、ゲーテは「黄金の空想よ」と記します。ゲーテの詩には、神話的なものと理知的なものが混在していて、これが魅力のように思います。ゲーテはゲルマン神話と、とくにギリシャ神話の影響が色濃いようです。
この詩集は生田春月が翻訳をした作品です。ゲーテは政治家としても活躍し、かのナポレオンからも尊敬されていた作家で、その言葉を詩で楽しめるというのは、なんだか嬉しいように思います。
(総ページ数/約10頁 ロード時間/約10秒)
『ゲーテ詩集』全文を読むにはこちらをクリックしてください
・top page ・本屋map ・図書館link ★おすすめ本 ★書籍&グッズ購入